SPECIAL ISSUE
特集
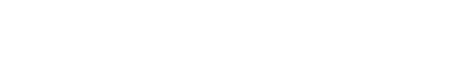

三輪眞弘〈オリンピックに向かう社会〉とイェリネク『スポーツ劇』のテキストから触発されたことを、各執筆者の研究分野と結びつけて自由に書いていただくリレー形式の特集記事です。『スポーツ劇』にはスポーツを巡る言説が散りばめられています。オリンピックの開催を2020年に控えている日本社会において、各エッセイを通じて読者や観客の皆さんが改めて思いを巡らせるきっかけになればと思っています。
かたやま・もりひで
1963年生まれ。音楽評論家、思想史研究者。専攻は政治学。2006年京都大学人文科学研究所より「戦前日本の作曲界の研究」で人文科学研究協会賞を授与される。2008年『音盤考現学』『音盤博物誌』で吉田秀和賞およびサントリー学芸賞受賞。2012年『未完のファシズム──「持たざる国」日本の運命』で司馬遼太郎賞受賞。慶應義塾大学法学部教授。
私は断じて思うのだが、スポーツは野蛮である。
春の早朝、学校のグラウンドに居た。小学校2年生のとき。サッカー部の練習だ。授業前の午前7時台に集まらねばならない。小学校といっても家の近所ではない。東京の都心の私立学校である。自宅から片道45分はかかった。午前6時すぎに家を出る。まだ満7歳だというのに。重いランドセルを背負い、電車に揺られ、最後は急勾配の坂の上を目指して懸命に駆け上がる。それでようやく学校だ。教室でサッカー着に着替え、運動場に整列。朝のグラウンドには、その頃、日が射さなくなってきていたのではなかったか。すぐ近くに建築中の高層ホテルの背が伸びてきて、次第に朝日をさえぎりはじめていた。そのせいで朝の寒さがいちだんと身に染みたように思う。
だったら行かなければいいではないか。サッカー部ということはクラブ活動だろう。入りたい者だけが入って、練習したい者だけが早朝に行くのだろう。すると私はサッカーがしたかったのか。サッカー部の早朝練習に参加したかったのか。そうではなかった。私にとって、運動は幼稚園の頃から走ることを除いては苦手だったし、でんぐりがえしにも鉄棒にも苦労していた。楽器の練習でも、指回りがあまりに悪く、教師を呆れさせていた。運動部に入りたいなどとは断じて思わなかった。ところが入った。なぜか。事実上、強制入部だったからである。
私の通っていた私立学校ではサッカーが校技として位置付けられていた。制服は、ヨーロッパのサッカー好きで有名な某国の昔の軍服を模しており、校内の催事として毎学期、クラス対抗のサッカー大会が催されていた。運動会と別にサッカー大会がある。運動会は秋だけだが、サッカー大会は年に3度もある。その日は一日中、サッカーをしている。体育の時間でも年柄年中、サッカーをしている。大会に勝つために練習をしなければならない。その練習時間に体育の授業があてられていた。
そのほかにサッカー部の活動もあった。小学校1・2年生時のクラス担任だった老教師は学校愛に充ち満ちていた。校技がサッカーであることを他の教師たちよりも一段高いレベルで誇りにしていた。サッカーが規律と道徳を生む。子供に秩序をもたらす。団体競技は魂の鍛練場である。担任教師の信念だった。
「サッカー部強制入部」はそんなクラス担任の独自方針。同じ学年でも他のクラスは違っていたと思う。緩かったはずである。だが私のクラスでは、校技であるサッカーを心の底から愛せない者は学校の門をくぐってはならず、教室の椅子に座る資格もなく、そういうサッカー愛の生徒自らによる表現の最善の手段はサッカー部への入部と早朝練習の参加と、相場が決められていた。
小学校2年生の一学期の始業式の日。ホーム・ルームの時間で担任教師から渡されたのは、学費の振込み票、給食費の降り込み票、それとサッカー部費の請求書だった。さすがに心も身体も幼すぎる小学校1年生はまだサッカー部に入部したくとも確か禁止であった。2年生からなのである。2年生から入れる。いや、入らねばならない。否も応もない。サッカー部に入らず早朝練習に参加しない者は校門をくぐってはならない。「非生徒」「クラス構成員外」のレッテルを貼られる。私はそのように認識していたし、クラス・メート全員がそのように考えていたし、入部の手続きをしたはずである。私でさえ入ったのだからそうだったのであろう。「非国民」のそしりからは免れたい。人はしばしばそう思うものだ。子供はいちだんとそうだ。敏感だ。私はきちんと空気を読み、体操着とは別のデザインの、学校指定によるサッカー着までわざわざ購入して、週に何度かの早朝練習に参加するようになった。
まだ何回目かというときのことだったろう。その日の早朝練習の課題はヘディングであった。ボールをヘッドで受ける。額の上のあたりで跳ね返す。サッカーの基本的な技のひとつである。私もサッカーの真似事を幼い頃からすでに何度もしていたし、体育の授業でサッカーをやりはじめてもいた。テレビ等でサッカーの試合を観戦することもあった。幼稚園のときのメキシコ・オリンピックで多少は火の付いた日本におけるサッカー・ブームの様子も少しは分かっていた。ヘディングについても知らないことはなかったし、体育の教師や上級生が間近でヘディングを行うのを実見してもいた。
しかし、自分でやるとなると話は別である。まだ一度も経験したことはなかった。ところが、その日の朝、いきなりヘディングをやれという。馬鹿な! サッカー・ボールだぞ。痛いに決まっているではないか。大いにひるんだ。でも練習せねばならないという。しないわけにはいかない。何しろサッカー部員なのだ。上級生が顔めがけてボールを投げつけてくる。みんな簡単にこなしている。私の番がきた。ただちにサッカー・ボールが飛んで来た。眼前に。どうする! からだが固まっている。何もできない。動かない。まずい。少し前に首を傾げて、ボールを受ければいいだけ。でも硬直しているものはしようがない。ぶつかる。ぶつかった。顔面に。強烈に。痛い。気が遠くなる。ボールを投げた上級生がすぐ正面に立っている。その目が点になってゆくのが朧気に分かる。熱いものが溢れてくる。鼻血だ。しかも両鼻からだ。噴出する。どんどん! グラウンドに血が垂れる。血だまりができる。血だまりに倒れ込む。ノックアウトされたボクシング選手のように。
つまりはサッカー・ボールを思いっきり鼻で受けて血まみれになって気絶したというわけだ。私はその日をもって、サッカー部を辞めることができた。練習の足を引っ張る不適格者と認定されたのだろう。ヘディングもできない前代未聞の生徒。いちおう傷痍軍人のようなものだから、サッカー部から退いてもクラスで「村八分」にされることはなかった。「名誉の負傷」、いや、あまりの不成績による「不名誉の負傷」とやはり言うべきなのかもしれないが、「命令」を守って「クラス構成員の義務」を果たし、健気に早朝練習に参加しての大流血事件だったから、まずは円満除隊。そういう体裁をとることができた。
そうして私はいちはやくサッカー部から解放され、早朝練習を心配することもなくなった。喜びを満喫した。だが、スポーツの暴力の神は私をまだ許してはいなかった。
私がサッカー部の練習で「名誉の負傷」をした翌月か翌々月のこと。昼休みに級友たちと運動場で野球をやっていた。野球といってもビニール・ボールとプラスチックのバットによる簡易なものだ。真似事だ。でもいちおう野球のつもりだった。
その野球はどんな状況下で行われていたか。広々とした草っ原で呑気にやっていたのか。そうではない。学校の運動場はコンクリート舗装だった。転ぶと極めて痛い。そこでサッカーも野球もしていた。しかも、そう広くはないグラウンドに、1年生から6年生までがひしめいている。何百人もがまちまちに動き回っている。過密も過密。おまけに、私たちが野球をやっていることから類推されるように、道具の使用も球技も禁止されていない。私たちの野球で内野手をやっている友達のすぐ横に、別の野球をしている上級生が背中を向けて立っている。そんな具合だ。狭いグラウンドの中でさまざまな球技の縄張りが幾重にも重複している。そのうえ野球のみならずサッカーをしている者まで居る。今、思えば、猛獣の居るアフリカの平原に裸で捨てられたくらいに、いや、東名自動車道か何かの道の真ん中に丸腰で捨てられて「どうぞ、はねられてください」と言われるくらいに危険である。それでも休み時間はグラウンドで遊ぶのが良い。運動をするのが良い。スポーツへの憧れを育てるのが良い。これはもう一種の信仰であろう。しかも、その信仰の上に日々繰り広げられる、「交通戦争」も真っ青の過密なグラウンドでのドラマから、大きな事故が起きたり、怪我人が出たという話は、不思議と聴いたことがなかった。その日の私の事故までは。
私はそのとき野球でピッチャーをしていた。フライやゴロや送球を捕球するような運動神経を有していないと周囲から認定されていたので、投げる役しか残らなかったのである。何球目だったろうか。投げようとした。投球フォームらしいかたちをしてみせた。サウスポーなので右足を上げて投げようとした。そこで記憶はとだえた。気が付くと医務室に寝かされていた。
聞くところによると、私が投球すべく片足立ちで腰高に不安定になった一瞬の虚をつくように、サッカー・ボールを追う上級生が横からしゃにむに突撃してきて私を突き飛ばしたのだという。私はグラウンドを覆うコンクリートにひどく頭を打ち、またも気絶した。ヘディングに失敗して血染めにしたばかりのグラウンドに、それからわずかの日を経ただけで再び沈んだ。サッカーの次は野球。ぶつかってきたのはサッカーをやる上級生。
私は意識を回復してからしばらく茫然としていた。ただ寝ていた。しばしたって母が迎えにきた。担任の教師が電話で自宅に知らせたものであろう。医務室の看護師は、ぶつけた頭が心配なのですぐ病院に連れてゆくようにと、母にすすめた。いま思えばなぜ救急車を呼んでくれなかったのか不思議な気もする。ともかく、自宅もよりの総合病院に、学校の近所からタクシーを拾って向かった。着いた病院の待合室で私は激しく嘔吐した。そのときの周囲の大人たちの戸惑いが忘れられない。私ももう駄目かもしれないと思った。
ようやく診察の順番が来た。医師は糸でつるされたコインを振り子の要領で左右に振ってみせた。そしてコインが幾つに見えるかと尋ねた。私はひとつに見えた。ひとつしかないものがひとつに見える。これでは異常なしではないか。けれど私は頭がまだボンヤリしていたし、ひどく調子が悪かった。野球とかサッカーとか学校とかいう危険な世界から離脱するように、私の心に何者かが絶対的命令を発していた。
「2つに見えます」。何の躊躇もなくそう答えた。医師は即座に私の入院を決定した。それから短いあいだ、私は危険から身を潜めて療養することができた。
そのあと、当然ながら長い学校生活が続いた。小学校、中学校、高等学校。同じ学園で12年をすごした。サッカー部からは小学校2年生の入部直後に真っ先に退けたとはいっても、校技のサッカーはいつまでも付いてまわる。サッカー大会に体育の時間。サッカーをやる。けっきょく高校までサッカーである。高校生のときの体育の授業では、グラウンド半面を使い、11人対11人ではなく、6人対6人で、ミニ・サッカーと称するものをやり続けた。リーグ戦で学期中ずっとやっている。6人は、フォワードとハーフが2人ずつ、バックとキーパーが1人ずつに編成されていたと思う。私はバックである。後衛である。サッカーをやるのは、特に小学校2年生の頃からもちろん猛烈に嫌いだが、観戦はそれなりに楽しめる人間に育っていた。授業でサッカーとなれば仕方ない。バックとして真面目に捨て身でゴールを守った。よく血みどろになった。顔面をサッカー・ボールが直撃することはどうしても時折ある。そういうときは鼻血である。眼鏡が鼻の表皮にめり込んで、裂傷を作って血が流れることもあった。
それからこんなことも。 ロング・シュートを阻止しようとした。着地点に先回りする。そのつもりだったのに目測を誤った。振り返ってボールを胴体に当てるはずだったのに、その前に、ボールに先んじて走っているつもりの私の後頭部をボールが直撃した。なぜだあ! ここまで見事に命中せずともよいではないか。けれど、不思議と衝撃は軽かった。カラスに蹴られた程度。なんともなかった。眼鏡を除いては。眼鏡は飛んでいった。走っている私の顔から眼鏡が離れた。ロケット・エンジンでも付いているかのようにビュワーンと飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ。走っても追いつかない。眼鏡がゴール・インした。キーパーの目が点になった。超現実的だ! これこそシュールだ!! と思ったら転んだ。膝を派手に擦りむいた。眼鏡はゴールの網にひっかかっていた。
体育の毎時間、捨て身の防衛戦が続いた。私は満身創痍である。そのかいあって、と私は信じていたのだが、チームの失点はとても少なかった。相手に1点も与えない試合も幾つもあった。ところがその学期についた体育の点数はとても低かった。100点満点で55点である。しょっちゅう負傷しているというのに、これはおかしい。体育の教師に文句を言いにいった。だが、彼はまったく動じない。データに基づく合理的採点を行っているという。キーパーは失点の少なさが評価につながり、他の生徒はシュート数や得点数をポイント化して、基礎点数に上積みして最終成績を出しているという。そう言えば体育の教師は毎回の授業終わりにその種のデータを生徒からの自己申告にしたがってまめまめしくとっていた。
「だからね、君の場合は、キーパーでもないし、シュートもしていないし、もちろん得点もあげていないわけだろ」。「そうですけど」。「だから基礎点数に何の上積みもないわけ。よって不合格にならないギリギリのところでね、55点のままなんだよ」。「でも眼鏡は壊すは、血も出して、顔だって傷だらけだし、眼鏡代だけでものすごいお金になってるんですよ。このディフェンスの仕事は評価されないんですか」。「専守防衛じゃ、点にならないよ。他の生徒はバックったって、前にあがってシュートすることもあるんだ。みんなそうなんだ。君だけだよ。このクラスで一回もシュートしたという申告にこなかったのは」。「でもディフェンスなんですから。役割に徹すればシュートしにいくはずないでしょう」。「専守防衛は国際的評価に値しないんだよ。攻撃に加わらないと。分かりますか」。「個別的自衛権だけではだめなんですか」。「駄目ですね。評価されたかったら、眼鏡を壊すだけではなく、シュートしなさい、シュート。男ならシュートだよ。男はシュートするんだ。分かったか。君は55点が正当な評価なんだ。くやしかったら攻撃しなさい」。
以上の会話の一部は、今日の状況をふまえた創作だけれども、大筋はそのままである。とにかく専守防衛が評価されなかったことの悔しさは三十数年経っても忘れられない。私の内に今も怒りがこみ上げてくる。
私は断じて思うのだが、やはりスポーツは野蛮である。スポーツの喜びは相手に血をしたたらせることと神話的底部においてつながっている。サッカーでたくさん血を流して笑い者にもなった少年の私、疑似的な死まで経験させられた少年の私には、そのことが深く刷り込まれた。体育やスポーツは、軍隊や戦争と、それから闘争本能や攻撃本能や破壊の快感や集団的規律の概念とどうしたって結び付く。専守防衛に身を粉にする者を愚かしいと蔑む。許せない。そんな私は断じて思うのだが、サッカーや野球に熱狂する国は特に野蛮である。
|補遺A|
でも私はサッカーも野球も観戦するのはけっこう好きだし、オリンピックを毛嫌いしているわけでもない。それはやはり人間の本能を刺激する。私のトラウマは、私を、スポーツすることからはある程度、遠ざけてはくれるが、闘争本能や攻撃本能まで消滅させることはできない。だから私は、スポーツを呪いながら、なおそれに喜べる面を普通の多くの人と同じく相変わらず平凡に有し続けている。
とにかくスポーツは、破壊や戦争の衝動を司る本隊の前を行く、偽装された前衛である。それは平和や健康や美や倫理や道徳や規律正しさの仮面を被ってはいるけれど、その実体は人間の攻撃的な本能に最も忠実なしもべである。前衛も本体も本能に結び付いているとすれば、人間のいる限りそれらを壊滅させることはできない。ならば、以下に如何に入れて安全に飼っておくかということになる。いずれにせよ、それらはなるべくおとなしくさせておくにこしたことはないのであって、本隊は悪しきものだが前衛は別ということはありえない。野蛮なものは魅力あるものだが、それを無批判的に肯定することはできない。
|補遺B|
昭和初期のことである。右翼思想家、大川周明がクーデターの計画を立てた。実行部隊にそれなりの人数がいる。でも残念ながら事前に計画的に準備できない。そこで当日にいきなり実行部隊を作りだしてしまう秘策を思い付いた。煽動者たちに失業者を集めさせる。日比谷公園に誘導する。そこに臨時の拳闘場を作って、野外で派手なボクシングの試合を、流血を伴ってみせる。むろん無料である。失業者を集めるのにも「ボクシングのいい試合がただで見られるから」という釣り餌を使い、本当にそれを見せるというプランである。その催事は合法的に準備されなくてはならない。とにかく大川周明によれば、ボクシングはスポーツといっても結局は殴り合いだから、内に不満を抱えた失業者たちがそれを野外で見物すれば、興奮をおさえられなくなり、暴力的衝動が最大限引き出されるに違いない。そこは煽動者たちのさじ加減でどうにでもなる。あとは簡単だ。日比谷公園の周囲には政府官庁と大財閥のオフィスが集まっている。ボクシングを見物する失業者の群れは、大川周明のイメージでは、たちまちバスティーユ監獄を襲撃した革命的民衆に変化する。彼らが日比谷と霞ヶ関と大手町を打ち壊す。スポーツによってこそ革命的内戦が開始されるのである。実行には移されなかったけれど。
|補遺C|
チェコのアニメ作家、ヤン・シュヴァンクマイエルの短篇アニメーション映画「男のゲーム」はスポーツと暴力のつながりを、きわめて本源的かつ、あまりにシンプルに表現している。作品は記録フィルムと粘土アニメとのコラージュである。記録フィルムはサッカーの国際試合での超満員の観客席を撮ったもの。熱狂、熱狂、また熱狂。昂ぶった群衆の姿がこれでもかと映し出す。一方、アニメの方では、粘土の選手たちがサッカーの試合を行うのだが、両チーム合わせて22人の選手たちは、みな同じ顔をしている。つまり集団主義によって画一化され、個性がない。しかもボールの蹴り合いは途中から殺し合いに変ずる。そして最後には22人全員が粘土による身体造型を徹底的に破壊され尽くして死に絶え、その情景を前にした観客の熱狂はとどまるところを知らないのである。
|補遺D|
中村真一郎に「死者たちのサッカー」という短編がある。1992年に『文學界』に発表された。一種の怪談小説。大学の守衛が夜中にグラウンドに見回りに行く。そこに幽霊が出る。大学病院で死んでいった患者たち。彼らはサッカーをする幽霊だ。守衛は幽霊たちに全身を粘土のように揉まれる。するとサッカー・ボールに変身してしまう。さんざんに蹴られる。翌朝、グラウンドの片隅で発見される。姿は人間に戻っている。でも満足に口をきけない。自分をサッカー・ボールのままと思い込んでいる。心をとざす。入院する。主筋はそれだけ。何のオチもない。しかし脇筋がある。けっこう長い。作家本人の重度の鬱病体験が綴られる。その思い出話だ。入院する。主治医に運動を勧められる。ピンポンをやってみる。長距離を歩く。世田谷から銀座まで歩く。確かに効く。回復が早まる。無心になれるのがよいようだ。手荒いスポーツの代表、サッカー。そのボールにされて丸められ、蹴りに蹴られて人間性を木っ端微塵にされる守衛。蹴る方も、大学病院に入れられるくらいの重病・難病に苦しみ、もしかすると誤診とかもあって、ストレス一杯に死んでいった人々。サッカーの暴力でストレスを解消する死者たち。その暴力に晒され、無気力に陥る生者。一方、お手柔らかなスポーツの代表、ビンポンと徒歩によって、それでゆっくりじっくり癒される作家。主筋と脇筋の対比が面白い。向きの正反対な筋書きが無造作に並行して放り出されている。そういう趣向である。
もちろん守衛がサッカー・ボールに変身して心をとざして丸まってしまうのは、内向の衝動の象徴的表現ということもあるだろう。カフカの『変身』を思い出す。中村の小説ではサラリーマンの守衛がボールに内向して丸まり、それがしかも作家の鬱病の記と重なる。守衛も鬱病なのだろう。激しい社会の暴力にさらされ続け、ついにアルマジロみたいに硬直したのか。そう思わせる。人が苛まれ変身し動かなくなる。これはもうカフカの『変身』である。毎日疲れ果てて家族を養い続けるセールスマンが虫に変身し、動けなくなり、邪魔者扱いされ、暴力を振るわれ、死に至る。「死者たちのサッカー」は『変身』と類似性が認められるようにも思われる。
虫やサッカー・ボールにならないためにどうするか。中村真一郎の『頼山陽とその時代』は、若き山陽が広島から江戸へと歩くことで鬱病を治したと特筆大書している。サッカーで血を流すのも面白いかもしれないが、ピンポンと徒歩くらいがやはりちょうどいいかもしれない。みなさん、もしもスポーツが大嫌いでも、適度な運動を忘れずに、心身の健康に留意いたしましょう。
(完)

