SPECIAL ISSUE
特集
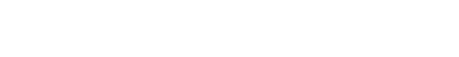

三輪眞弘〈オリンピックに向かう社会〉とイェリネク『スポーツ劇』のテキストから触発されたことを、各執筆者の研究分野と結びつけて自由に書いていただくリレー形式の特集記事です。『スポーツ劇』にはスポーツを巡る言説が散りばめられています。オリンピックの開催を2020年に控えている日本社会において、各エッセイを通じて読者や観客の皆さんが改めて思いを巡らせるきっかけになればと思っています。
いいだ・ゆたか
1979年広島県生まれ。専門はメディア論、文化社会学。著書に『テレビが見世物だったころー初期テレビジョンの考古学』(2016年)、編著に『メディア技術史ーデジタル社会の系譜と行方』(2013年)、共著に『ヤンキー人類学』(2014年)など。現在、立命館大学産業社会学部准教授。
1.スポーツとメディア
スポーツとはまったく無縁の生活を送っている。テレビでスポーツ観戦をすることも滅多にない。
ところが、メディアを専門に研究していると、どうしてもスポーツとの関わりを避けて通ることができない。たとえば、駅前広場や特設会場などでスポーツ中継を観戦するパブリック・ビューイング。一度も参加したことはないけれど、新しい放送文化という意味で、そのあり方には強く興味を抱いている。
また、新聞社や放送局はスポーツ・イベントを主催し、みずから報道や中継をおこなう。こうした事業活動は大正期以降、日本特有のかたちで展開され、紙面や電波を通じた言論・表現活動とならんで、マスメディアという営みが近代社会に定着していくうえで大きな役割を果たしてきた。
いわゆる「夏の甲子園」(=全国高等学校野球選手権大会)の前身にあたる「全国中等学校優勝野球大会」が、大阪の豊中球場で初めて開かれたのは1915年。国民の身体を西欧的基準に規格化することを目指し、簡易保険事業の一環として「ラジオ体操」が始まるのは1928年のことである。戦前、ラジオによる野球中継の全盛期は1931年から33年までの3年間で、早慶戦を山場とする六大学野球が実況放送の中心だった。ラジオ雑誌ではこのころ、次のように述べられている。
野球熱が一般民衆間に普及したる最大要因は実はラヂオによる中継放送であると思ふ。ラヂオは野球のために其大衆的実用価値を認められ、野球はまたラヂオによりて急加速度を以て民衆化せられたのである。即ちラヂオと野球とは今や全く不可分の相互関係によつて連結せられて居るのである。(1)
正力松太郎が読売新聞社の事業戦略の一環として、ベーブ・ルースやルー・ゲーリックらを擁する大リーグ選手チームを招聘したのを機に、大日本東京野球倶楽部(東京巨人軍)が設立されるのは1934年、プロ野球のペナントレースが始まるのは1936年のことである。
そして戦後、正力による日本テレビ放送網の設立にともなって、日本社会にプロ野球中継が根付いていった。この当時、早稲田大学の学生だった小林信彦が言うように、「テレビ放送の初期というと、必ず街頭テレビの話題が出てくるが、あれはプロレスと野球に興味がない人間にとっては関係がない」(2)。
1974年に『テレビジョン ―技術と文化形式(Television: Technology and Cultural Form)』という本を著した文芸批評家のレイモンド・ウィリアムズは、放送技術の形式が整備されていく過程において、本来これに先立つべき内容についてはほとんど定義されなかったことに着目している。
内容の問題が提起されると、おおむね付随的に解決された。これらの新しい技術手段によって送信されたのは、国家的な盛儀、大衆的なスポーツ・イヴェント、舞台演劇などであった。(3)
この指摘を裏付けるかのように、近年、オリンピックやサッカー・ワールドカップ(以下、W杯)などのスポーツ・イベントがパブリック・ビューイングで受容されるばかりか、舞台演劇などを映画館やライブハウスのスクリーンで鑑賞する「ライブ・ビューイング」も、ここ数年で市場規模が急速に拡大している。
こうしてマス・コミュニケーションの歴史をたどっていくと、近代スポーツはつねに、メディアによって支えられているという以上に、互いにその重要な一部を構成していることが分かる。もちろんオリンピックも例外ではない。
2.ナショナリズムとインターナショナリズム
吉見俊哉によれば、1932年に開催されたロサンゼルス大会以降、オリンピック報道は、国際的なスポーツ競技の結果を単純に事実として伝えるだけでなく、それを国家間の象徴的争いと見なす政治的な暗喩が多用されていく。そして、オリンピックをめぐる語りが政治性を帯びていく背景には、そうした語りを伝えるメディア自体が、より視覚的かつ同時的なものに変容してきたという前提条件があった(4)。
1936年のベルリン大会では、アドルフ・ヒトラーの号令のもと、レニ・リーフェンシュタールによって記録映画『民族の祭典』『美の祭典』が制作され、スタジアムに参集した十数万人の観衆をはるかに超える人びとの意識を動員する、メディアに媒介された祝祭の可能性を予感させた。
かつて舞踏家だったリーフェンシュタールにとって、オリンピックを撮るということは、まさに「スポーツ劇」を演出することだった。それは「単純にナチ的であるとは形容しがたい特質が備わっていたがゆえに、ほかに例がないほど、ナチズムの肯定的なイメージを国際的に普及させること」(5)ができた。
ゲオルグ・モッセによれば、ドイツ体操運動(トゥルネン)をはじめとして、19世紀以前からドイツに存在した諸々の大衆運動を通じて、国家的な儀礼の中に運動する身体が動員され、「大衆の国民化」が進行していった(6)。伊藤守が指摘するように、こうした規律訓練的な身体文化の伝統と、競技スポーツの身体性が折り重なった地点に出現する「美」に、リーフェンシュタールはこだわり続けた(7)。
ドイツから亡命したふたりの哲学者、テオドール・アドルノとマックス・ホルクハイマーは大戦中、「今日では外界が映画の中で識った世界のストレートな延長であるかのように錯覚させることは、簡単にできるようにな」り、「実世界はもはやトーキーと区別できなくなりつつある」という見方を示している(8)。
ちなみに、宣伝相のヨーゼフ・ゲッベルスは、ベルリン大会でテレビによる実況中継放送を構想し、実験的で不完全なものであったが、それを実現させている。ダフ・ハート・デイヴィスによれば、「テレビを別にすれば、オリンピックのために開発された技術装置にはほとんど問題がなかった」という(9)。
1940年に開催が予定されていた東京大会は、日本が東洋の盟主であるという帝国主義的な意識と結びついて構想され、「国威発揚」の格好の機会と見なされていた。当然、テレビの実況中継放送の実現も不可欠だった。その経緯については、拙著『テレビが見世物だったころ』で詳しく検証している(10)。
こうしたテクノ・ナショナリズムも含めて、目に見えやすい国家間の対立だけが、オリンピックをめぐる政治ではない。近代オリンピックはその起源から、人種、ジェンダー、ナショナリティなどの構築に関わる、複数の「政治的なるもの」を多層的に内包していた(11)。イェリネクの『スポーツ劇』の中では、近代スポーツの背後に潜む「政治的なるもの」たちが、複雑にせめぎあっている。
ロサンゼルス大会、ベルリン大会、幻の東京大会が、日本における国民意識の形成といかに結びついたかについては、浜田幸絵『日本におけるメディア・オリンピックの誕生』という労作が出版されたばかりであり(12)、2020年の東京オリンピックが触媒となって、今後も考証や議論が深まっていくだろう。
3.言説と情動
ダニエル・ダヤーンとエリユ・カッツは1992年、『メディア・イベント―歴史をつくるメディア・セレモニー(Media Events: The Live Broadcasting of History)』という本を著した。メディア・イベントとは、生放送と局外中継の大規模な組み合わせによって、日常の放送の流れが中断され、視聴者のあいだに特別な連帯の感情をもたらす「マス・コミュニケーションの特別な祭日」とされる(13)。この意味において、オリンピックやW杯などのテレビ中継は、アポロ11号の月面着陸、ダイアナとチャールズのロイヤル・ウェディングなどと匹敵する、典型的なメディア・イベントと捉えられる。
ふたりの研究が、日常の時間の流れから切断された次元に成立する、全国あるいは全世界の視線が集まるような国家的イベントに焦点を絞っていたのに対して、日本ではどちらかといえば、冒頭で述べたとおり、新聞社や放送局の事業活動など、もっと規模の小さな、日常との境界が曖昧なイベントにこそ、強い関心が向けられてきた。
いずれにしても、メディアに媒介されたイベントは、人びとに強烈な共有体験をもたらし、「われわれ」としての集合的記憶を強化するとともに、他者との境界を確認させる同化作用がある。新聞社や放送局が主導するスポーツ・イベントはしばしば、読者や視聴者に働きかけて大衆の国民化を実現する手法、あるいはナショナリズムを高揚する手段として採用されたと言われる。
もっとも、ナショナリズムとインターナショナリズムのあいだを揺れ動くスポーツ言説とは異なる角度から、われわれの受容経験を説明しようとする試みもある。たとえば、英語圏の文化研究においては2000年代以降、言語や言説などの意味作用と区別される、「情動(affect/affection)」という概念に注目が集まっている。大山真司はサッカー観戦にそくして、これを次のように説明する。
ストライカーが素晴らしいゴールを決めた瞬間、すべての観客は、情動のレベルで必ず強く反応します。「鳥肌が立ち」「思わず」「席から腰が浮く」状態がそうかもしれません。しかしその反応は、一瞬にして感情のレベルでは歓喜と落胆に分かれます。情動は意識以前、あるいは個人化・社会化する以前の、表象もラベルも貼られなければ構造化もされない身体の状態であり、一方、歓喜や落胆は感情であるためにすでに個人的、社会的領域に属します。(14)
伊藤守によれば、「情報が伝わる」という現象は、「認知」や「認識」といった意識化された活動に関するものだけでなく、「情熱」や「意欲」、「感情」や「情動」といった、無意識の、意識化されないけれども何ごとか身体に作用するものでもある(15)。三輪眞弘も「オリンピックに向かう社会」の中で示唆しているように、言説と情動は互いに異なる次元で互いに干渉し合い、われわれの経験の質を規定している。
4.同化と異化
日本にパブリック・ビューイングが定着したのは2002年の日韓共催W杯にまで遡るが、こうした集合的沸騰に対して、批判的な言説も存在した。香山リカが当時、路上などで無邪気に国旗を振る日本の若者たちを「ぷちナショナリズム症候群」と評したことは、特に大きく話題になった(16)。しかしながら、こうした批判の妥当性は、実証的には明らかにされてこなかったといえよう。
リビングにおける家族同士よりも密着して、試合の動向に一喜一憂し、感動を分かち合う。家庭内視聴では決して味わえないパブリック・ビューイングの一体感は、しばしば半世紀以上前の「街頭テレビ」を取りまく熱狂に喩えられる。
もっとも現在では、テレビ中継が会場の巨大スクリーンで視聴されるのみならず、手のひらのスマートフォンでも同時に情報が収集され、ソーシャルメディアなどを通じて声援や野次が拡散していく。かつての新聞やテレビは、大衆の感情を動員する手段になり得たかもしれないが、われわれの生活がデジタルメディアによって多層的に媒介されている現実の中で、それは決して容易なことではない。同じ場所で祝祭的な経験を共有していながら、われわれの意識はそうした局在性をやすやすと超えてしまう。
2006年のドイツW杯においても、ドイツ国内では大規模なパブリック・ビューイングが開かれた。試合を観戦するためのスクリーンが仮設されているだけでなく、ステージ上では音楽フェスティバルが催され、露店が立ち並ぶ路上では、ダンスや小競り合いが繰り広げられたという。参加者が熱狂的なサッカーファンだったとは限らない。さほど試合内容に関心を向けることなく、流行のイベントを楽しむために会場を訪れた人びとも数多く存在していた(17)。
このような傾向は、日本で90年代後半以降、夏の風物詩として定着した野外ロック・フェスティバル(夏フェス)と共通している。通常のコンサートやライブとは異なり、フェスの来場者は経験を積むほど、必ずしもステージ上の音楽には執着しなくなり、現在では幅広い世代の人びとが、思い思いに会場の雰囲気を楽しむようになっている。
特定の音楽趣味を共有した集団としてフェスの観衆を捉えることが不可能であるように、パブリック・ビューイングの参加者も、それが特定の指向性を持った群集―熱狂的なサッカーファンもしくは感情的な愛国主義者―であると見なすことはできない。
テレビだけでなく、インターネットに媒介されたスポーツ中継も、今後ますます増えていくだろう。そしてその受容体験は、ネット上で日々、日常的に実践されている擬似的な集団視聴(いわゆる弾幕文化)と切り離して考えることはできない。ウェブ社会におけるメディア・イベント概念の変容については、今年中に論文集を出版したいと考えている。
今から4年後、僕は相変わらず、スポーツとは無縁の生活を送っているに違いない。それでも、東京オリンピックは一生に一度のことだから……と自分に言い聞かせ、パブリック・ビューイングに初めて参加しているかもしれない。そうだとすれば、さほど競技の内容に関心を向けることなく、スマートフォンを片手に会場の雰囲気を味わっていることだろう。それでも群集の中で浮かない程度には、集合的沸騰に同化してみせるかもしれない。
オリンピックに向かう日本社会の中では、イェリネクが警告するように、スポーツをめぐる狂騒や幻惑に同化し、その背後に潜む暴力に対する不感症に陥ってしまうことには、細心の注意を払わなければならない。それでもなお、スクリーンに媒介された群集の雑種性や複数性こそを直視し、そこから生まれ得るかもしれない異化効果に、一縷の望みを託してみたい。
注
(1)『ラヂオの日本』1930年7月号、1頁。
(2)小林信彦『テレビの黄金時代』文春文庫、2005年、22頁。
(3)レイモンド・ウィリアムズ「テレビと社会」デイヴィッド・クローリー/ポール・ヘイヤー編『歴史のなかのコミュニケーション ―メディア革命の社会文化史』林進/大久保公雄訳、新曜社、1995年(原著=1974年)、286頁。
(4)吉見俊哉「幻の東京オリンピックをめぐって」津金澤聰廣/有山輝雄編『戦時期日本のメディア・イベント』世界思想社、1998年。
(5)ライナー・ローター『レーニ・リーフェンシュタール ―美の誘惑者』瀬川裕司訳、青土社、2009年(原著=2000年)、141頁。
(6)ジョージ・L・モッセ『大衆の国民化 ―ナチズムに至る政治シンボルと大衆文化』佐藤卓己/佐藤八寿子訳、柏書房、1996年(原著=1975年)。
(7)伊藤守「規律化した身体の誘惑 ―ベルリン・オリンピックと『オリンピア』」清水論編『オリンピック・スタディーズ ―複数の経験・複数の政治』せりか書房、2004年。
(8)ホルクハイマー/アドルノ『啓蒙の弁証法 ―哲学的断想』徳永恂訳、岩波文庫、2007年(原著=1947年)、262頁。
(9)ダフ・ハート・デイヴィス『ヒトラーへの聖火 ―ベルリン・オリンピック』岸本完司訳、東京書籍、1988年、172頁。
(10)飯田豊『テレビが見世物だったころ ―初期テレビジョンの考古学』青弓社、2016年。
(11)清水編、前掲書。
(12)浜田幸絵『日本におけるベルリン・オリンピックの誕生 ―ロサンゼルス・ベルリン・東京』ミネルヴァ書房、2016年。
(13)ダニエル・ダヤーン/エリユ・カッツ『メディア・イベント ―歴史をつくるメディア・セレモニー』浅見克彦訳、青弓社、1996年(原著=1992年)。
(14)大山真司「ニュー・カルチュラル・スタディーズ02 ―情動的転回?」『5 ―Designing Media Ecology』2号、2014年、79頁。
(15)伊藤守『情動の権力 ―メディアと共振する身体』せりか書房、2013年
(16)香山リカ(『ぷちナショナリズム症候群 ―若者たちのニッポン主義』中公新書ラクレ、2002年。
(17)飯田豊/立石祥子「複合メディア環境における「メディア・イベント」概念の射程 ―〈仮設文化〉の人類学に向けて」『立命館産業社会論集』51巻1号、2015年。

