SPECIAL ISSUE
特集
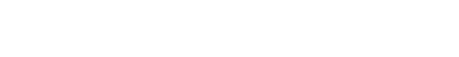
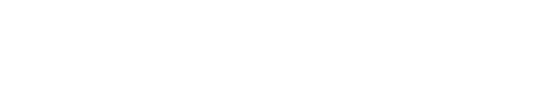
三輪眞弘〈オリンピックに向かう社会〉とイェリネク『スポーツ劇』のテキストから触発されたことを、各執筆者の研究分野と結びつけて自由に書いていただくリレー形式の特集記事です。『スポーツ劇』にはスポーツを巡る言説が散りばめられています。オリンピックの開催を2020年に控えている日本社会において、各エッセイを通じて読者や観客の皆さんが改めて思いを巡らせるきっかけになればと思っています。
さわらぎ・のい
美術批評家。1962年生まれ。同志社大学文学部を卒業後、東京を拠点に批評活動を始める。最初の評論集『シミュレーショニズム』(1991年)で90年代の文化動向を導くものとして広く論議を呼び、主著『日本・現代・美術』では日本の美術史・美術批評を根本から問い直した。他に1970年・大阪万博の批評的再発掘を手がけた『戦争と万博』など著書多数。最新刊に『後美術論』(第25回吉田秀和賞受賞)。多摩美術大学美術学部教授。
オリンピックという催しについての感覚が、以前とだいぶ違っているような気がしてならない。言うまでもなく、過去に日本でオリンピックが開かれたのは、1964年の夏季東京五輪、1972年の冬季札幌五輪、1998年の冬季長野五輪の三度で、2020年に無事、二度目の夏季東京五輪が開かれれば、都合四度目ということになる。私は1962年の生まれだから、そのうち三度の五輪を経て今に至っていることになる。加えて2020年の五輪へと至る過程も逐一見聞きしている。ただし、最初の東京五輪の時はまだ2歳になってまもなかったから、記憶にはまったく残っていない。ところが近い過去ほどよく覚えているかというと、必ずしもそういうことはないようだ。その証拠に、三十代の頃に開かれた長野五輪については、ほとんどまったく記憶に残っていない。長野五輪がなぜここまで記憶に残っていないのかは、それはそれで注目に値する気もするけれども、いずれにしても、今日に至る私の生涯で、もっとも深く心に刻まれているオリンピックは、したがって9歳の時に札幌で開かれた冬季五輪大会ということになる。教育年齢でいうと小学校4年生の時のことだ。まだ子供である。けれども、2020年の東京五輪の開催意義にしばしば「子供たちに夢を与える」というのが掲げられるので、ちょうどその時分に、世界の耳目を集める国民的な祭典を経験したことにはなる。それならば、新しい東京五輪についても、自分なりに振り返ってみるだけの意義はあるだろう。そう、はたして小学生の私は、そのことで夢を与えられただろうか。
答えは微妙である。というのも、幼い私は、確かに札幌五輪で繰り広げられる様々な競技をテレビを通じて食い入るように見ていた。まぎれもなく興奮していた。だが、いまこうして改めて記憶の紐をたぐってみると、意外なことに気づく。いま興奮と書いたけれども、それでいて、ナショナリズムに通じるような興奮はまったく覚えがないのだ。
ちなみに、札幌五輪でもっとも世を賑わせたのは、宮の森で開かれた70メートル級スキージャンプ競技である。並みいる強豪国を向こうにまわし、1位から3位までの金・銀・銅を笠谷、金野、青地の各日本選手が独占した。当然、国内は熱狂の渦となり、彼らは「日の丸飛行隊」と呼ばれ、その戦果を讃えられた。しかし、これではまるで特攻隊ではないか。戦争を賛美する極右主義の台頭が危惧される現在では、そんな語句が新聞の見出しを飾り、公共放送の実況でアナウンサーが口走ろうものなら、ネットを中心に袋叩きになるのは避けられまい。けれども、うまく言えないのだけれども、そこまで露骨に戦争を連想させる賛美であったにもかかわらず、そのことで国民はなんらナショナリズムをあおられていなかった。少なくとも、自分はそうだった。それはなぜだろう。
正直、このスキージャンプ競技の日本選手による金・銀・銅の独占には、私自身、少なからず心が踊った。けれどもそれは、次の日にはスキーの滑降競技、回転、大回転、そして距離競技(当時はすべてこう呼んだ。もちろんスノーボードなど存在しない)、そしてボブスレーやリュージュ、さらにはバイアスロンといった未知の競技への関心によって中和されていた。そして、そこで直面したのは、日本での開催という栄えある立場にあるにもかかわらず、日本選手の上位入賞はおろか、78位とか81位とか、へたをするとそれ以前に予選落ちして順位がつかない様子だった。しかし、それで私は夢を失ったかというと、そんなことはなかった。日本選手が冬季大会の花形であるスキーを中心とする主要競技では世界にまったく通用しないというのは、夢ではなく当たり前の現実で、だからといって別段、落胆することもなかったのだ。それよりも私が興奮したのは、たとえば射撃とスキーを組み合わせたバイアスロンという競技の選手が纏う不思議ないでたちや、標的を外すと周回場を余分に滑らなければならなくなる変わったペナルティの仕組みだった。つまり、世界にはまだ、なにやら未知の競技やルールがあるということに興奮したのだった。そして、そういう競技への関心は、日本選手の健闘や日本そのものへの声援とは、まったく結びついていなかった。声援するにも、そもそも下位すぎて画面に出てこない。裏返せば、当時はそんな競技でも平気でテレビを通じて中継していた。今ならきっと「日本人が活躍しない競技など延々と放送するな」と文句が出るだろう。当時は、自分が所属する国家としての日本への応援と、五輪という競技への関心が、今ほど密接には結びついていなかったのだ。
だから、スキーのジャンプ競技で笠谷が活躍すれば、それはそれで応援したけれども、他方では、日本選手が出てくる競技でも、外国にもっと好きな選手がいれば、迷いなくそちらを応援した。アイスホッケーなどでは、チェコスロヴァキアの闘い方が好きだったから、チェコスロヴァキア人でもないのに彼らを激しく応援したし、そういう贔屓のチームがいる場合には、日本との試合であっても敵方を応援した。その結果、日本が負ければ小気味よく感じたし、そのことに疑問も感じなかった。日本よりも強くてかっこいいのだから、当たり前のことだった。ゆえに、そういう立場をおおっぴらにしても、まわりから別にとやかく言われることもなかった。まわりの友達にも、ソ連が好きだったり、カナダが好きだったりと個別に贔屓のチームがいて、それぞれバラバラに試合を見ていたからだ。
こうしたことは、今ではちょっと考えられない。たとえばサッカーのワールド・カップ、日本戦の実況で、別に自分とはなんの縁もないのに、「敵」国のチームのユニフォームや戦い方が好きだというだけの理由で、相手方を応援などしようものなら、「お前なに考えてるんだ」ということになるだろう。場合によっては袋叩きになってもおかしくない。しかしそういう圧力を、少なくとも札幌五輪の時に小学生だった私はまったく感じていなかった。
その結果、どうなったか。先に書いたとおり、日本を応援する以前に、日本と世界とのあいだには歴然とした実力の差があること、そして、日本が世界に勝つためには、今とはまったく違う工夫が必要であること、さらにはこの差は、日本人が一致団結して声援したり、一選手の根性でどうにかなるようなことでは最初からないというのを、小学生なりに理解した。同時にそれは、克服することがひどくむずかしいという点で、子供達に本来の意味での「夢」を抱かせることになったとも言える。最初に、果たして自分は五輪を通じて夢を与えられたかという回顧に「微妙だ」と答えたのは、そういうことだ。そしてこの微妙な「夢」は、いま生業としてみずから関わる領域で、美術をどういうものと考え、どうやって論じていくかという基底にも、まちがいなく繋がっている。
けれども、いま新たな東京五輪を目前にして語られる「夢」は、これはまったく性質を異にしている。そこで掲げられる「強い日本」という理想は、なんら現実に根ざしていない。かつて私が札幌五輪を通じて抱くことになった未来の夢は、「世界には日本よりもはるかに強靭で魅力的な可能性がある」という実情に根ざしていた。ところが、いま語られる「夢」は、これとはほとんど真逆を向いている。少なくとも私は、これからの日本を生きる子どもたちに、そんな虚言など植えつけてほしくない。率直に言って、嘘にほからないからだ。五輪招致のための方便とされた福島原発事故は制御下にあるという「悪・夢」は、その最たるものだろう。

