SPECIAL ISSUE
特集
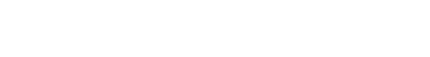
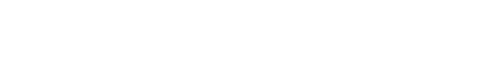
3年目を迎えるKAAT神奈川芸術劇場と地点の共同制作。第三弾は新作『駈込ミ訴ヘ』と、昨年初演した『トカトントンと』再演の二本立て公演となる。2012年12月22日、制作過程や創作意図について演出家・三浦基自身が稽古場で語る、KAATとの共同制作では恒例のプレストークを開催。今回は音楽評論家、思想史研究者の片山杜秀氏をゲストに迎えたトークとの二部構成で、太宰治の作家性や原作「駈込み訴え」の背景についてなど、深い分析と洞察による対話が繰り広げられた。以降は新作を巡る部分の採録である。
構成・文:大堀久美子
かたやま・もりひで
1963年生まれ。音楽評論家、思想史研究者。専攻は政治学。
著書に『音盤考現学』『音盤博物誌』『クラシック迷宮図書館(正・続)』『線量計と機関銃─ラジオ・カタヤマ【震災篇】』(以上、アルテスパブリッシング)、『国の死に方』(新潮新書)、『未完のファシズム』(新潮選書)、『近代日本の右翼思想』(講談社選書メチエ)、『ゴジラと日の丸』(文藝春秋)など。朝日新聞、産経新聞、『レコード芸術』『CDジャーナル』等で音楽評を執筆。
人文科学研究協会賞、第18回吉田秀和賞、第30回サントリー学芸賞を受賞。慶應義塾大学法学部准教授。
太宰を泳がせる言葉のプール
三浦 2012年11月にフェスティバル/トーキョーでエルフリーデ・イェリネクの『光のない。』を演出したのですが、片山さんにはその舞台を観劇後、ポストトークにも出演していただいて、非常に刺激的なお話が出来ました。今日はその続きをという思いもあってゲストをお願いしました。
片山 気軽にお引き受けしたのですが、その後、作品資料としていただいたものには太宰治はもちろん、天皇制やキリスト教をめぐる種々の提起があり「大変なことを引き受けてしまった」と心配しながらやってきました(笑)。
三浦 片山さんにとって太宰はどういう位置づけの作家ですか?
片山 出会ったのはいかにも生意気ですがいちおう小学生です。私は当時から文庫本マニアで、特定の作家というより新潮文庫なら新潮文庫を全部集めて読もうとする癖があって。その一環として「人間失格」「走れメロス」など小学生で読みました。どの程度理解していたかは甚だ疑問ですが。
あとはやはり小説そのものよりも、太宰治の伝記的な情報に気持ちが行ってしまって。お嬢さんの太田治子さんの手記を原作にした「斜陽のおもかげ」という吉永小百合主演の映画をテレビで見たというような。
客観的に知ろうとすれば、共産党の運動に関わったことなど、伝記的な部分でも男女関係に限らぬ話題がいくつもある。それを前提に読めば、特に戦中戦後の一連の作品は、日本の歴史とよくシンクロしているともう少し分かったかもしれない。が、どうしても世間のイメージに引きずられて整理しきれないでいた作家でしたね。その点で、三浦さんの舞台『トカトントンと』からは、衝撃的に教えられることが多かった。「今の歳まで太宰を分かっていなくてスミマセン」と思いましたから。
三浦 太宰をやりたいということは、以前から漠然と考えていたんです。でも、どの小説を舞台に置くか考えたとき、自伝的でスキャンダルな内容の作品は無理だと思った。いわゆる私小説を俳優が演じて、舞台上に太宰のように居ることは恥ずかしいと思ったんですよね。
「文学の演劇化」は昔からよくやられているし、主役を作家本人に設定し、「作家を演じる」ことも珍しくはない。でも僕は、それでは演劇にならないだろうと考えていた。ただの作家礼讃で文学の置き換えになってしまう。だから『トカトントンと』に関しては玉音放送、天皇の言葉を劇中に配した。あのテキストは天皇個人が書いたものではなく検閲もあり、色々な思惑が盛り込まれた匿名性の高い言葉ですよね。憲法などと同じように、作家性は非常に希薄です。
そういう言葉が演劇のテキストに入ってくることで、太宰の書いたもの、ひいては「太宰治」そのものがポンと浮かび上がってくるプールのようなものをこしらえることができる。そこに太宰を放り込み泳がせることで、作家と作品を浮き彫りにし、捉え直す仕掛けを『トカトントンと』で僕はつくったんだと思います。玉音放送はプールの水。今度の『駈込ミ訴ヘ』では何がプールの水になるのか、今の稽古場ではそれを試行錯誤している状態です。
片山 そこにキリスト教が出て来るわけですね。聖書の言葉でプールを満たせるか、と。
「父なるもの」と「母なるもの」
三浦 基本的な構造は、そういうことです。原作の「駈込み訴え」はキリストを密告するユダを巡る、聖書の話を翻案した小説という言い方もできる。元来がそういう構造の作品なので、聖書の言葉だけでなくオペラ歌手である青戸知さんにも出演していただき、讃美歌などキリスト教に関連している歌や言葉と、俳優の持っている言葉が駆け引きしてくれればと考えています。そもそも太宰とキリスト教の関係は、どこに遡るのでしょう?
片山 聖書のテキストや断片を太宰が自作に引用するようになったのは昭和10年代以降なので、子供の頃からキリスト教や聖書が近しかった訳ではないようですね。いきなり瑣末な話で皆さんの興味を削ぐかもしれませんが、太宰は聖書そのもの以前に、内村鑑三の弟子である塚本虎二が発行していた「聖書知識」という雑誌を毎月のように読んでいたらしい。塚本の聖書解釈に沿った形で、太宰は自作中でのキリスト教理解を行っているというのが、誠実な太宰研究者の見解だと思います。
共産党から転向させられた後、別の規範を求めていた太宰が聖書に出会った。というか「聖書知識」に出会った。以降、いくつもの太宰作品に聖書の引用が見られるようになったんです。
三浦 なるほど。
片山 太宰はなぜキリスト教に惹かれたのか。彼は共産党で、運動のために党から強烈なエゴイズムを押しつけられる。一方的に強圧的に命令してくるのが共産党ですね。猛烈に父権的なわけです。これは「駈込み訴え」のキリストとユダ、どれだけユダが奉仕してもキリストはお礼も言わない関係に重なります。でもキリストは共産党と違って優しく純粋で美しいところもある。つまり太宰はキリストのなかに「父なるもの」と「母なるもの」、一方的な要求ばかりしてくる人と包み込んでくれる人の両方を見ているのではないか、と。
地主で政治家も出すような旧家・津島家に生まれたことで、四男坊の太宰は最初から「いらない人間」として乳母に育てられたりしている。長男優先という父権的な制度に弾かれ、父から家から相手にされず、居場所を失い、代わりの父を共産主義に求めるけれどそこにも居つけない。父権的なものに失望し、母性的なものに向かう太宰が必要とした媒介項としてキリスト教はあった。
ここでキリストと天皇のイメージがだぶって来る。父権的なものへの恐怖が太宰にはあるから、母性的なものとしての天皇は良い、と。その証拠があるかと言われると困るのですが、戦後、「これからの日本人は自由に、アナキスト的に生きるべきだ。絶対自由人である我々国民を包む形で天皇はいるのだ」という太宰の主張にも合致するように私には思える。職業作家としてある意味真面目な人だったから、戦時中は時代に寄り添ったものも書いたけれど、それは父権的な天皇への絶対忠誠ではなかった。天皇は認めるけれど、それは自分たちの自由をも認めて包んでくれる、母なる存在なればこそ、という願望が常に太宰の作品にはある。
天皇とキリスト教の問題、大もとにある津島家での疎外感などが重なり、父なるものと母なるものとのあいだの葛藤について延々とひとり語りする「駈込み訴へ」のような作品を、太宰に書かせたのではないかというのが、私の勝手な思いですね。
坂口安吾との対照性
三浦 太宰は自分の葛藤や愚痴を真面目に書く作家なんですよ。稽古場で聞く「駈込み訴え」の言葉は、キリスト教どうこう以前に太宰特有の愚痴なんだとつくづく思う。自由を欲し、それを認めてくれる人を求め、けれどいざその自由を得た瞬間に何が書けるかと言えば愚痴や文句ばかり、ということが太宰の文体の根底にある気がする。そんな小市民的な感覚が受けて、「斜陽」などはベストセラーになったんじゃないか、と。
もうひとつ、「津軽」に代表されるような青森との関係。非常に父権制の強い津島家と僻地である故郷から逃げるように上京し、帝大に入った太宰は、東京の現実を見て失望したように僕には思えるんです。僕は斜陽館に泊まったことがあるけれど、レンガ造りの西洋建築を取り入れた非常に立派な建物で。そんな実家とそれを取り巻く状況を比べてみると、東京は大したことがないと、空虚感を感じたんじゃないか、と。
実家や故郷に対して、共産党の運動に対して、キリスト教に対して、など太宰は常に真面目に向かい、それらに失望した瞬間に大きく針が振れ、壮大な愚痴が溢れて作品となる。それが太宰の創作のメカニズムのように思えるんですよね。
ついでに訊きますが、坂口安吾についてどうお考えですか? 安吾は太宰が死んだとき「不良少年とキリスト」という愛情の裏返しのような文章を発表していますが。
片山 確かに太宰と安吾をセットにして考えると、見えてくるものが多くありますね。同じ無頼派ですが、安吾は捕物帳や推理小説から文明批評のようなルポルタージュまで書いている。ものすごく批評的で客観的。執筆の対象を新聞記者や論理学者のように外から見ることができるのが太宰と一番対照的なところではないでしょうか。それに対して太宰はいつも内側から当事者として見てしまう。
三浦 そうか、つまり安吾は三人称で語ることができるということだ。だから偉そうなんですね、安吾の文体は(笑)。きちんと物事を語るから感想としては正しいというか。正しいと思って読めるけれど、太宰の場合は一人称で書くから、読者が二人称にされ「(作家が)私に訴えている」と勘違いしてしまう。そこが差なんだな。
片山 安吾の「堕落論」も、「日本人は一回全部堕落しろ」とか偉そうですよね。
三浦 女々しいしズルにも程があると思いつつ、どうしても太宰に引きつけられてしまうのは、その一人称の語り口なんですね。人前で発語することを考えたとき、太宰の文章・発言は面白いし演劇に向いていると思う。こしらえたプールのなかで泳がせると、ビビッドに聞こえてくる種類の言葉なのかなと。『トカトントンと』はそれがバッチリはまって、観客の想像力も豊かになったと思うんです。片山さんなら『駈込ミ訴ヘ』をどう演出しますか?
片山 演出なんてそんな(笑)。でも音楽を重視するという方向性は既に出ているんですよね?あとは玉音放送みたいな短いテキストならばともかく、聖書の言葉を使う場合はどこを持ってくるかという問題がありますし。ただ、音楽はプールをつくりやすいけれど、そこに頼り過ぎるのはね。言葉でプールをつくるのが地点の魅力だと思うので、そこに良いバランスがあると上手くいくんじゃないかと個人的には思います。
言葉と音楽の関係
三浦 プールの話でいうと、音楽を使うのは大変難しいですね。特に状況音やノイズではなく、歌詞を伴う楽曲を使う場合は。節や音符がついた途端、言葉は本来とは違った記号になっていく。最近は音楽家とのコラボレーションを増やし、少しずつ利用の仕方のコツもわかってきたけれど、まだ僕の創作に十分は馴染んでいない。僕の作品の台詞回しは「音楽的」とも言われるけれど、自分ではよくわかっていないし、声にも言葉にも意味しか求めていない。意味を追い求めていった結果、今のように言葉を分断したりメロディアスな発語になっていったのだけど、それもまだ、自分では上手く説明ができていなくて。
片山 『光のない。』のときはヴァイオリンの開放弦の音程を合唱がゆっくり積み重ねていって、羊の鳴き声に変わっていくのを舞台の背景というか、言葉と関係ない形で上手く使っていらした。「音」が舞台の言葉とセットになり、けれど音と言葉がどう関係してるかはなかなかわからないまま、ずっといく。で、これは合唱はヴァイオリンの真似をしていて、ヴァイオリンの弦はもともと羊の腸で作られていたもので、羊は家畜の象徴で、しかもキリスト教では人間は「神の子羊」だから、この鳴っている音は地震と津波と原発事故の犠牲者の叫びなんだなとついに気づく。そこに理解が及ぶまで非常に時間がかかる。言葉と音楽の関係が謎のまま緊張を保って、でもだんだん解けてくる。これがよかった。お客さんに最初からわかりすぎる選曲、音の使い方ではないほうが良いでしょう。言葉の海=音の海みたいな層と、太宰の言葉の層とが反応して観客の感覚を狂わせるような相乗効果を生み出す「距離」があるほうが。
三浦 今のは感情の問題ですよね。感情がベタっと舞台上に存在しないように、というのは僕の仕事の一番中心的なところだから、讃美歌や聖歌のような言葉のある歌の扱いは丁寧にしないと危険ですね。
片山 そう、折角三浦さんが仕掛けたことに対する観客の緊張感が、歌や歌詞を「わかった!」と観客が思うことで続かなくなったら勿体ないと、ファンとしては思います。
神は「許します」とは言ってくれない
三浦 もう少しキリスト教の話をしておきたいのですが……「何故キリスト教か」というところが、ちょっと背伸びはしているけれど今回の創作のテーマのひとつであり、これは太宰にとっても、当時の日本人にとっても当てはまることだと思うんです。社会学的見地から言えば、日本人にとってキリスト教は本当は遠いもの。でも民主化、近代化していくうえで重要視されてきた経過がある。
最近にわか勉強しまして、現代社会の基盤である資本主義の成立と流布に、キリスト教は深く関わっているのではないか、と。そのへんのことを今、私たちのいる日本でどう考えていったらいいのか、そのヒントが欲しいんです。
片山 それは大テーマですね……私個人の話からすると、小学校から高校までカトリック系の学校に通っていたので、信者ではないけれどキリスト教は常に身近にあり、自分なりのイメージはある。一言で言えば、マックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」の問題になって、「人間は天職を持って真面目にコツコツやらなくちゃいけない」となり、それが産業社会とセットになると果てしない資本蓄積、どこまで蓄積しても「もっと真面目にやります」と働き続けなければいけなくなる。
こういうメカニズムを発動させたのはカトリックよりもプロテスタンティズムで、カトリックはむしろ資本を蓄積することに反対していた。教会という厳正な権力があるから、資本を蓄積して教会に貢いでもまだ余りがあると、教会に対して脅威になる金満家が出てくるから、「お金を貯めるのは罪。教会に献金してあとは一銭も持つな、全部使ってしまえ」と浪費を蓄財より推奨した。ある意味ヨーロッパの文明が進むことを妨げていた部分もあります。
でもプロテスタンティズムは、既成の教会は信じるに値せずと言い出した。一人一人がコツコツ真面目に働き、蓄財することが神への信仰心の表れ。懸命に自分の役割と向き合うこと、それのみが人間の生きる道というふうに教えてしまう。その教えが、生きている限り果てしない、止めることが出来ない、ブレーキがかからないという状況をつくり出してしまった。
これは個人的なことですが、中学生の頃、良くないことをしたとき跪いたことがあるんです(笑)。ああいうとき跪くという行為を一回でもしてしまうともうダメで、神は「許します」とは言ってくれませんから、「どこまでいけば許されるんだろう?」と無間地獄に入っていく。ヨーロッパ人は、キリスト教を入口に、信仰も経済も無間地獄に入ってしまっているから止まれないのだと思います。
それが資本主義であり、科学の発展と金儲けのグローバリズムなんでしょうね。人間の「豊かになりたい」という欲望は、宗教と関係ない単純に現世的なものだと思うかもしれないけれど、意外やそうではないんです。全然ヒントになっていない気がしますが。
三浦 全然なりません(笑)。ただ、その仕組みはすごく良くわかりました。今お話しいただいたようなことが、客席で何となくわかる、「あっ」と思えたとき、演劇はすごく豊かになるんですよ。それが『トカトントンと』の場合、玉音放送の存在だった。玉音放送がパーンと今、この瞬間と繋がる瞬間があり、それが日本の天皇制を考えることとも繋がった。
今のお話の無間地獄、ブレーキがかからない現状は、我々も今日本で経験していることだから、そういうことと繋がりたい、演劇という表現を介して。そのとき初めて芸術が宗教を超えられる。
太宰は「無宗教、無思想だから芸術に特化して生き抜く」というような言い方をどこかでしていたけれど、キリスト教なるものが何かふと感じられれば、『駈込ミ訴ヘ』をやる価値があるかなと思ってはいます。
プールを満たすものがあるとすれば
片山 さっき「言葉で満たす」という表現をしていたけれど、キリスト教を感じる、キリスト教の神を感じるということは、プールに水が入ってない状態のほうが表現し得るのかもしれないですね。お客さんにはちょっとツラいかもしれないけれど、ただ太宰の言葉だけが浮遊して、プールには何も見えない、みたいな。
玉音放送の衝撃は、天皇という決して国民一般には語りかけてこなかった存在が声をラジオで発してしまった衝撃でしょう。しかも天皇の詔書というのは黙読するためのテキストで本来音読用ではないでしょう。音読するのは勅語ですよ。ところが昭和天皇は終戦の詔書を朗読してしまった。声にならないはずのものが声になってしまう違和感と衝撃は、世代を超えて我々になお現在まで伝わってくる。そんな天皇の声は「満たすもの」には効果的だけど、キリスト教の神を感じさせるのは跪いても声のない状態だから『駈込ミ訴ヘ』は玉音放送みたいなもので満たすことが本当に難しい。満たせるものがあるとすれば無。沈黙で満たす。そんな気がしてきました。
三浦 なるほど、僕はわかってきましたよ。今日のお話は、この後の創作に良い刺激にきっとなっていくと思います。
2012年12月22日「『駈込ミ訴ヘ』『トカトントンと』について語る会」
at KAAT神奈川芸術劇場 中スタジオ より採録

