SPECIAL ISSUE
特集
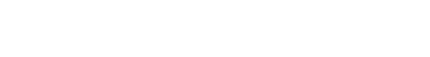

去る2月19日に下北沢B&Bにて行われた映画『ドストエフスキーと愛に生きる』関連トークイベントの一部をご紹介します。なぜ「悪霊」なのか、演劇がいま出来る仕事とは? 字幕翻訳家の太田直子さん、映画監督の森達也さんとのやりとりの中で、地点『悪霊』にかける演出家・三浦基の思いが語られます。
――本日は『ドストエフスキーと愛に生きる』のプレイベントにお越しいただきありがとうございます。2月22日から公開となる本作に先駆けて、この作品とドストエフスキー、ドキュメンタリーひいては翻訳についてのお話を三人の他分野でご活躍の方々からお話をうかがいたいと思います。劇団「地点」で舞台演出をされていて、3月14日から『悪霊』の公演を予定されている三浦基さん、映画の字幕翻訳をされている翻訳家の太田直子さん、映像作家の森達也さんをお迎えしました。
本作はドストエフスキーの五大長編作品を生涯をかけて翻訳された、スヴェトラーナ・マイヤーというウクライナ・キエフ生まれの女性の半生を追ったドキュメンタリーです。84歳のスヴェトラーナの生活が静かに丁寧に描かれ、心に響く作品となっております。
皆さまがどのような感想をお持ちになられたか、まずは三浦さんからお伺いできればと思います。
三浦 予告編にも一瞬映っていましたけど、彼女は翻訳した文章を自分で読むんです。タイピストの前でしゃべって、原稿も、原文を読みながら声にしてしゃべるんですね。それで、タイピングしている人と、前のシーンのどこそことおなじだから、ここは同じ単語ですか、というやり取りをしながら進めていくんですね。恐ろしく時間がかかりますよね。普通は翻訳家だと自分で手書きなり、打つなりしてやりますよね。そこに他者が介在しているっていうのはおもしろい。さらに、これも一瞬だけ映ってましたけど、スヴェトラーナさんの前にひとりのおじさんがいて、おじさんは音楽家と紹介されるんですけど、その人が第二稿みたいな形でタイピングした原稿を読み始めるんです。そこでまた、おじさんがごねるんですよ。ここは意味がわからないって、またやり取りをする。コンマを入れといたほうがいいんじゃないか、いや、原文には入ってないって、そういうコミカルなやり取りがあって、それが一番印象的でした。つまり翻訳作業を、この人の場合年齢的な問題もあるんだろうけど、ひとつのスタイルとして、タイピングしてもらう人、朗読してもらう人というように他者を通して翻訳をしていくというか、声で確認していく、ということをするわけですよ。
まあ、恐ろしく時間がかかるなあって思ったんですけど、僕の仕事もどちらかという俳優の声を聞きながら修正をしていくという作業なので、親近感を持ちました。
――『ドストエフスキーと愛に生きる』のオフィシャルブックを作るにあたって、翻訳家さんのお仕事場を見学していろいろお話をうかがったのですが、やはり、二者三者が関わって翻訳をするのはとてもユニークな手法だと、いろいろな方がおっしゃっていました。太田さんはいかがでしたか?
太田 わたしは、今三浦さんがおっしゃっていた翻訳作法、あれは驚きましたし、面白いなと思いました。主人公のスヴェトラーナさんは、ウクライナのキエフ出身で、20歳くらいにドイツに移住して、そのままずっと住んでいるわけですから、ほぼドイツ語ネイティブといってもいいかもしれません。ですが、彼女の母語はやはりロシア語なんですね。普通だったら、翻訳というのは外国語を母語に訳するというのが普通なんですね。逆は難しすぎます。私は外国映画に日本語の字幕をつけています。それはかろうじてやれますけど、逆をやれといわれたら、日本語の映画を外国の輸出用に英語の字幕を作りなさいといわれたら、私には不可能です。彼女もひょっとしたら、その点で、タイピストの人とか、本読みをしてくれる人がドイツ語ネイティブであること、その人たちのフィルターを通して万全を期しているということなのかなと思いました。
また、彼女の日常風景がとても美しくて、丁寧な手作業、いろんな料理をつくったり、アイロンをかけたり、ああいった生活の丁寧なところが翻訳にも反映しているはずだと。このオフィシャルブックでも多くの人がおっしゃっていて、ああそうだなと思ったんです。わが身を振り返ると、自分がずぼらで生活が乱れまくってますから、私はあまり翻訳者向きではないのかなと、そんなことも思いました。
――森さんはいかがでしょうか?
森 お二人が言ってくれたことにそんなに加えることはないんですが。まず、今日のこの催しを最初に打診されたとき、僕相当ごねましたよね。最近しょっちゅうごねてるんだけど、ほんとに本気でごねたんですよ今回は。何でかと言うと、作品に必要ないと思ったんですよね。ただもう映画を見るだけで十分、それに対して解釈したり、解説したりというのはまったく必要ない。それはどのようにみんなが解釈するか、ゆだねられるのであって、作った人間でない者、ましてや監督でない第三者が、したり顔して言うことはない。まあでもとても熱心に口説かれたので。
翻訳について改めてこの映画を見ながら面白い作業なんだなって。こんなに示唆にあふれた、言葉をただ単に翻訳するんではなくて、いろんな文化であったり、そういった萌芽みたいなものも感じさせてくれるし、あとね、カメラがすごいんですよ。とても斬新な撮り方をしているんですよ。あんまり言っちゃうとあれですけど、例えば、ドラマでも同じなんですけど、主人公が何かを見ている、そうすると次のカットでその見ている何かが映る、そういったモンタージュをすることで、その主人公に感情移入するわけです。自分もその主人公・登場人物になったかのような気になる、自分の目線の先にずれがあるかのように思う。徹底してそのモンタージュを拒否しているんです。スヴェトラーナさんをあたかも、ここにあるコップのように、ライトスタンドのように撮っている。それ以上の撮り方をあえてしていないんです。それによって逆にスヴェトラーナさんに対する僕たちの目線、自分は彼女を見ているんだということがはっきりする。感情移入によって彼女に安易に憑依しないような撮り方をしている。特にドキュメンタリーというのは手持ちでパンしたりズームしたり簡単にしちゃうんですよね。それを一切しない。見事なまでにフィックスで撮っているんですよ。それは見るときに気をつけてみていただければ、なるほどと思わしてくれるかも知れません。面白い見方じゃないかなと思いました。
――映像がほとんど動かない作品で、動いたなと思うのは電車で移動するシーンと、車で移動するシーンで、あとはずっとフィックスしていますね。
森 電車の中、ウクライナに行く途中に、車掌さんが話しかけてきて、それに対して彼女がいろいろしゃべるシーンがあるでしょう。まったくカメラ動かないんです。車掌さん一度も出てこないんです。あのシーンはすごいと思った。あれ絶対生半可なカメラマンだったら振り向きますよ。一切抑制して、あんなに禁欲的なカメラワークちょっと見たことないですよ。生半可な憑依をしない。見ている自分を意識しちゃう。スヴェトラーナさんを見ている自分。つまり、自分がいてスクリーンがあって彼女がいるわけでしょう。でも見ているうちに、自分が彼女自身になったり、彼女の心情になったり、目線になったりするわけで、これは映画的な文法なんだけど、あえてでしょ、これを拒否しているんですよ。それはすごいラジカルな関係ですよ。
――三浦さんなぜ今回「悪霊」を選ばれたのか、お聞かせ願えますか。
三浦 通常演劇作品を上演をする場合は、テキストの中でも戯曲というジャンル、上演を前提としたものを扱うのですが、ここ数年は小説を演劇にできないかということをやり続けています。太宰治の短編「トカトントン」とか、「駈込み訴え」とか。その前の年は本番がそんなにできなかったんですけれども、芥川龍之介の作品をコラージュした作品をつくりました。まあそういう流れがありまして、小説を演劇化してみたいと。一方で、ライフワークとしてチェーホフの四大戯曲を上演してきたという経緯もあるものですから、どうせやるなら小説家で一番エライのに挑戦したらいいやと思って、何のあれもなく、ドストエフスキーをやろうと思いました。ドストエフスキーにかんしては、中学生のとき、初めて長編を自分で最後まで読めたのが「罪と罰」だったんですね。ドストエフスキーはもちろんチェーホフよりちょっと上の世代なんですけど、気にはなっていた作家だったので、今まで短編をやってきたから、長編を思い切ってぎゅっと圧縮して2時間以内でやってみたら面白いんじゃないかなという直感ですね。
いま稽古の真っ最中なんですけど、台詞の部分がめちゃくちゃ多くて、鍵括弧の部分だけ抜いていってもひとつの長編戯曲になるくらいでびっくりしているところなんです。そういう意味では、すごく身近には感じています。僕はどちらかというと、その後輩・後世のチェーホフを通してドストエフスキーを見ているというところが大きいかもしれません。で、なぜドストエフスキーのなかで「悪霊」かといいますと、先ほどの映画でも五本の長編があると紹介されていたように、いつか五本ともやるんじゃないかなと思ったんです。最初に一番しんどそうな「悪霊」を選んだのは、どうせ一発目やるなら、一番難解そうなものをやってみたらいいんじゃないかな、と。また、よく言われるんですけれど、「悪霊」はポリフォニック(多声的)、いろんな声が渦巻いているということもありますし、その部分は僕がやってきた仕事で少し何かつながるものができるんじゃないかなと、淡い期待を持ってやってます。
多声性については説明するのが大変困難なんですけれども、要は登場人物がすごく沢山出てくる。先ほどお話に出たロシア人の名前が長いどころの話じゃなくて、上下巻通して、これだれだっけ?これだれだっけ?の連続で、常にいろんな人間、有象無象が登場してくるという魅力もあるので、誰が誰でもいいじゃないかという、言葉、声だけがずっと渦巻いているような感じがひとつ特徴としてはあると思います。もうひとつの最大の特徴は普通は小説って言うと、語り手がいて作者がいてこの部屋は白い何とかで、電球が何個あってっていう風景描写をするという人が神の目でいて、それの中にこういうシンポジウムがあって、三人座っていて「三浦曰く・・・」って言うことなんですよ。でも「悪霊」の場合は「G」という登場人物がいて、まあドストエフスキーと言ってもいいと思いますけれど、語り手も登場人物として出てくるんですよね。で、Gが登場人物たちとしゃべるって言うシーンがとても面白くて。下巻になるとだんだんGが消滅していって普通の小説になるきらいがあるんですけど、登場人物としての語り手が事件のあるところに入って行くっていうことがすごく面白くて、そこは創作する上で手がかりになると思って「悪霊」を選びました。
――太田さんは「悪霊」はドストエフスキー文学の中ではどういった位置づけなのでしょうか?
太田 まあ、位置といいますか、いわゆる大長編というのがあって、最初に「罪と罰」それから「白痴」で三番目の長編が「悪霊」ということになります。そのあと「未成年」「カラマーゾフ」ということになりますが、「悪霊」が一番政治色が強いというか、もともとこの小説って言うのは現実に革命家の内ゲバというかリンチ殺人事件が起きて、それに触発されて、ドストエフスキーがなんてこったというか、非常に興奮しまして、とにかくこいつらをこてんぱんに滑稽に描いてやるという、それが最初の動機だったみたいなんですね。それがだんだん書いているうちに、主人公のスタヴローギンという非常にどんよりとした深刻な人物が登場してきて、それで単純に政治的な揶揄をするような作品ではなく、あのような重厚長大な物語になったわけです。わたしの中ではドストエフスキーを読み始めてから、爆笑したのは「悪霊」が初めてで、ああドストエフスキーって笑えるんだなと思って。ある意味一番お気に入りの作品ではあります。あとまあ、父親の世代と、革命運動を起こす息子たちの世代が描かれていますが、ドストエフスキーは父の世代として責任を感じていた、我々がこいつら、この若者たちをおかしくしてしまったんじゃないかという意識もはたらいていたようですね。
――その「悪霊」が書かれていた時代背景についてもお話いただいてもよろしいでしょうか。
太田 書かれたのは1871年、日本でいうと明治4年ですか。その当時ちょうど西欧から新しい思想がロシアに入ってきて、それに若者たちがかぶれてしまう、というか飲み込まれてしまって、よし国を転覆してしまえと。皇帝とか、帝政をぶっ壊してしまえという革命の意識で若者たちがどたばた走り回るという形になってます。ですから、当然弾圧の対象にはなるわけですし、逆に言うと、革命家たちを揶揄したという側面でロシア革命後のソ連時代には発禁とまでとはいかないんですけど革命を誹謗したけしからん書であるということで、「悪霊」はあまり取り上げられない状態にはなっていましたね。
――「悪霊」には登場人物は何人くらい出てくるんですか?
三浦 原作だと、恐ろしいくらいで30人ちかいですよね・・・
太田 もっといるかもしれませんね
三浦 ま、主要な人物でも20人以上いますよね。大長編ですね。絞り込んでも主要な登場人物はだいたい12~13人になるんじゃないかな。オーソドックスな演出、例えばテレビドラマにしたり映画にしたりするにしても12~13人といったところではないでしょうか。僕は9名でいまやっています。ただ、僕の場合は、ひとりの俳優がひとつの役でやるっていうわけではないので、ひとりの俳優が複数に渡る役どころの台詞をいったり、あるいは今回もまた小説ですから、地の文章があったり、必ずしも、人数と役名が合致するわけではないんですけど。まあ、今回は一人一役にちかい形で進めています。たださきほども言いましたように、Gというドストエフスキーらしき人物の扱いが工夫すべきところで、それは小説を読者として読んでいても非常に面白い点だと思います。どこにカメラがあるのか、どこから世界を見ているのか。内部に入り込んでいったり、途端に俯瞰したり、そういったカメラワークというのかな、もちろんこの時代は、映画がまだない時代ですけれども。ドストエフスキーの功績っていうのは偉大で、僕らはもう映像技術を知っているから、いつのまにかこう、世界を俯瞰した視点というものを認識できるわけですけれども、ドストエフスキーの小説っていうのはその先駆け的な思考を持っているんだと思います。それを今回演劇で表現できたらいいなと思っているんですけれども。
――ドキュメンタリーの映像をつくり、ノンフィクションの執筆もされている森さんにとって、翻訳という行為をどのようにお考えになられますか。
森 ドキュメンタリーの作法としては、現場に行ってその状況を、世界を丸ごと咀嚼して解釈してそれを編集したり、そういったまあ後処理をしていくんですよね。それはまさしく翻訳といっしょで、翻訳は「私はそれが好きです」というフレーズがあったとしても、それを訳しただけでは意味がなくて、全体をまずつかんだ上で、その言葉をどのような文脈で出てきたものとするのか、場合によってはそれによっては言葉がかわったりもするわけですよね。まさしく「ポリフォニー」ですよね。言葉っていうのはひとつの言葉でも多義性のある、いろんな意味があるわけですよね。
例えば「A」という映画を撮って発表したときに、気になってしようがないから、劇場の片隅のほうで見ていると、誰かにみつかって「やっと真実を知ることができた。メディアは嘘ばかりついていたんですね」といわれて、とても困ったことがあるんです。これは僕の真実であって、あなたの真実じゃないでしょうと、とてもそっけない話をして当惑させちゃったんですが。あのときオウムの施設に行ってカメラをまわして僕は作品を作ったわけですけれども、そのときにもしじゃあね、三浦さんがカメラをもって同じ場所の同じ時間にいたとしても、同じ作品になるかといったら全然違うわけですよね。もっと極論で言えば、自動カメラみたいな人を介さないカメラだけを現場に置いてカメラが勝手に撮って、それを編集して作品になるかって言ったらできるわけないです。編集はできないです。なぜならば、世界を解釈できないわけですよ。つまり、現場にいるってことは映像撮る事が目的だけれども、自分がそこに身をおいて世界を肌身で感じる。それで初めて編集するという方向性が見えてくるわけで。だからいきなり素材だけもらっても編集しようがないですよね。そういう意味合いでは、翻訳とドキュメンタリーっていうのはきわめて近いものであると監督は言っているんだと思いますよね。で、そのインタビューで監督がなんていってたかな、客観性はありえないだったかな、これも普段言っていることですが、つまり、自分が解釈するわけですから、僕がオウムを解釈して編集するわけですよね。で、三浦さんも多分僕とは解釈が違うわけですよね。当然違う素材になるし、違う編集になるわけですから、じゃあそれ客観ですかと。もちろん一つ一つは客観ですよ。現実の断片ですよ。それをつむぐことで、テキスタイルすることで、自分の主観になるわけですよね。それがドキュメンタリーですから、それには客観なんてものはない。ニーチェがよく言っているみたいな、「事実はない、あるのは解釈だけだ」ということですよね。そういうことになるんじゃないかと思います。
太田 よく誤訳を批判されることもあって、確かに、誤訳はダメなんです。しちゃいけないんです。でも、ぶっちゃけあります。書物にも、映画にも。それで開き直るわけじゃないんですけれども、やはりその人の解釈だったり、100%な完璧な翻訳が世の中にあるかって言うとないと思います。たとえば私は「罪と罰」がだいすきだから、100%ロシア語のニュアンスをすべて汲みつくして日本語にしてみせますと山にこもって100年くらい暮らしてやってたらできるのかな・・・無理でしょうね。それってもう自己満足の世界になってしますので、もちろん中途半端はいけませんけれども、多少傷があってもとにかく世の中にこういう作品がありますから、読んでくださいと提示することも大事かなと思っています。脱線しちゃったかもしれませんが。
――先ほど三浦さんがおっしゃっていた「多声性」、「ポリフォニー」について、森さんからお聞かせ願えますでしょうか。
森 その前に、言葉そのものについてもいいでしょうか。江藤首相補佐官がYouTubeに7日に動画を発表したんですけど、靖国参拝についてアメリカが失望したというコメントを出したことに自分は失望したという動画をだしたんです。それを今日撤回しているんですよね。政治家っていうのは言葉の生き物ですから、言葉が一番大事なはずなのに、とても軽くなっているでしょう。いろんな違和感あるけれど、特にやっぱり言葉をみんながあまりにも大事にしていない。そもそも日本語ってそうなんですよね。アーカイブ、つまり文書として記録するってことがなかなか日本人てできないんですよ。戦後ね。これって一番大きな欠陥で、それこそ福島第一原発のあとの、原発調査委員会の議事録全部残っていないって、こんなのありえないですよ。でもそれが現実に起こっているんです。要するにエクリチュール、文書に対しての意識・緊張感がない。パロールなんですよ、チャットですよね。しゃべり言葉によって形成されている文化で、民主主義を形成するためには大きな欠陥なんですよね。言葉ってものを僕らはもうちょっと考えなきゃいけない。
なんでそうなっちゃったかっていうと、柄谷行人さんがいっているのは、日本語って言うのはカタカナがあって、漢字があって多義的過ぎる、悪い意味で多義的過ぎると。そこで要するに、ああいうカタカナを使ったら外来語、あるいは漢字を使ったら抽象概念を現すのだという意識付けをなされてしまうが故に、言葉っていうものを現実にコミットできなくなってしまう。という分析もあったりするんですけれども。みなさん思い出してほしいんですけど、十年前のドキュメンタリーあるいは報道番組の海外物の場合、ほぼ字幕テロップだったんですよ。いまではほぼ「ボイスオーバー」、つまりアフレコになってしまっている、で、その理由は明らかで楽なんですよ。やっぱり字幕ってじっと見なきゃいけないわけですよ。テレビってそれがダメなんです。アフレコにしてしまうと、おしゃべりしながら、何か食べながらみかんむきながらでもある程度分かるわけですよね。だから結果そちらに流れてしまっていて。でも声って大事なんですよ。いろんな情報があるんですよね。三浦さんは三浦さんのキャラクターがあり、この体格があり、この個性・パーソナリティーがあるからこの声なんですよね。太田さんもそうだし、僕もそうですよね。みなさんもそうです。
日本の文化はどんどん楽な方向にいっていて、それにメディアがあわせてしまっていて、その結果その声という大事なニュアンスをみんなが軽視してしまっているというのは重要な問題です。字幕というのは制限もあるんですが、入りきらないとかいろいろテレビ関係者は言うんだけれど、かつてそれでやってきたし、損なわれるものが多いんだったら字幕に戻すべきだと僕は思うんだけれどダメでしょうね。一旦人間は楽になっちゃうとなかなか元に戻れないから。由々しき問題だなって思っています。アメリカなんか結構映画を吹き替えたりするでしょう。
太田 外国は本当に全て吹き替えみたいですね。テクニカルな問題として、確かに声はとっても大切だと思います。映画が好きな人ほど字幕派ですね。字幕派です、字幕じゃないと見る気しませんっておっしゃる人は多いんですけれども。字幕よりは吹き替えとかボイスオーバーでしゃべったほうが情報としては多く入る訳ですよ。字幕だと情報をカットしなきゃいけないんですね。私たち字幕やっててもっときちんと伝えたいんだけど字数制限があって3割くらいはしょってしまいましたとか、そういう点で、ものすごく早口でインタビューに答えたりしていると、これだったら吹き替え・ボイスオーバーにしたほうが情報・内容としてはお客さんに伝わるかなと思ってしまうこともあるんですが、いまおっしゃったように、その人本来の声というのもすごく大切な情報ですし、そういったところは私も困るところなんですけれど。
森 だからプラスマイナスもちろんあるんですよね。情報量は圧倒的にボイスオーバーのほうが多いんだけれど、でも声というものが損なわれる、そこでプラスマイナス考えたときに、どっちが得かっていう言い方もへんだけど、僕は明らかに声を失うことのほうがデメリットが大きいと思うんですよね。3年位前に、NHKがポーランドの映画監督のアンジェイ・ワイダのドキュメンタリーをオンエアして、基本彼のインタビューを中心にしたドキュメンタリーだったんですけど、全部ボイスオーバーだったんです。僕はアンジェイ・ワイダの声が聞きたかったのに、全く聞こえなかった。その後ディレクターに会ったので伝えたところ、きょとんとして、え、なんかいけないですかみたいな感じで、説明したら初めてああそうなのかと言っていましたけど。それは悔しいですね。
テレビってもう半世紀以上このダーウィニズム的にいかに視聴率取れるかってやってきているんで、それは半端じゃないですよ。いまの形っていうのは進化系の最終体みたいなものでね。それはやはり試行錯誤していますからね。いまもテレビどうしようもない、何で朝っぱらからオリンピックばっかりやっているんだとかみんな思うけどそれは結局数字がきているんですよね。だからやっているわけで。そういうことでいうとメディアって言うのは僕たち自身ですよね。政治も同じです。ポピュリズムですから。だからメディアは三流だけど、国民は一流だとか、政治は一流だけど国民は二流とかそんな国ないですよ。もう国民のレベルがあってメディアがあって政治がある、そう思います。
声って舞台でどうですか?
三浦 安部首相のことで言うとね、オリンピックの演説のときに「アンダーコントロール」で有名になったように、彼の英語は立派だったと思うんですよね。日本語だと滑舌が悪いんだけど、英語はずいぶん稽古したのか非常に自信に満ちている。でもそれ全部嘘だねということはみんな分かっていてそれは言葉の問題でもあるのかなと。安部首相に関してもオリンピックだアンダーコントロールだということ自体を演じているという言い方をすれば、うそをついている、それが母国ではない。それを療法の彼の日本語とああいったシチュエーションをみんな見ているわけですよね。そこでの違和感というか。本人の言葉じゃない、言葉っていうのが嘘をつく側だっていうことを少し探っているのかなと森さんのお話をきいていて考えていました。そういう意味では先ほどから指摘されている問題というのは、民主主義の問題でもそうなんだけど、やはり、政治が言葉だという文法があるとすると、その日本語自体の構造がすごく難しい、曖昧だとよく言われますけど。西洋哲学であったり、「罪と贖罪」の問題もそうなんだけど、宗教の問題も絡んでくるだろうと、いまドストエフスキーを稽古してて思うことなんですよね。根底に流れているコンテクスト、文脈というものが決定的に違うんだと。自分たちが持っている言葉の構造自体が違うんだっていうことをあえて翻訳劇をやることによってお客さんとともに、まだ違和感のレベルでしかないかもしれないけれど、認識することは演劇が今もまだ果たせる役割なのではないかと思っています。
僕がやっている仕事、演劇が本当かって言われればもちろん嘘・フィクションで、今回も例えば暗殺さるシャートフを演じる人間がいるわけですよね。それをまさかシャートフ本人だとは思わない。さきほどの映画で挿入シーンはミステイクだと森さんがおっしゃったのは僕も同意見で、あそこ見ているときにちょっと気恥ずかしかったんですよね。ラスコーリニコフの苦悩を説明的に演じているだけで、どうも余剰になってしまった。ノンフィクションのドキュメンタリー映画の中にフィクショナルな映像をいれると、ああいう風にバランスを欠くんだなと見ていて思いました。そこを逆照射してやっていくのが僕の仕事であり、お客さんはまずは違和感をもってもらうしかしようがない、というところからまずは始まるのかなと。ドストエフスキーの「悪霊」もそうですし、「罪と罰」もそうなんですけど、「あなたは無神論なんですか?」という問いが非常に鋭く問われているわけですね。ドストエフスキーは敬虔な信者なわけです。でも彼がフィクションを書き始める、もちろんノンフィクションの題材から書き始めたときに迷うわけですよね。迷っていて、もしかしたら神を信じる美しい話とか、先ほどもラスコーリニコフの罪を悔いるのか、償うのかという問題も指摘されていましたけど、やはり最後までその結論を書かない・書けない、迷っている、いい意味でのお喋りだと思うんです。ロジックじゃなくて、しゃべっているうちにこうこうこういう思考回路になっていきましたっていうのが彼のエクリチュール・文体だとおもいます。そういう意味では、すこし遠い存在のロシア正教、宗教の問題、西洋哲学、日本人には感覚的に理解できるヨーロッパへのコンプレックスといった主題も含めてドストエフスキーにせよチェーホフにせよ、日本人にとってはロシア文学っていうのが身近なのかなと。そこを入り口にして、われわれはグローバルに物事を考えられる言葉の文法をおそらく知っているんだけれども、でもやっぱり分からないということをドストエフスキーを通して描けるんじゃないかなと期待しているのかな。初めの質問にもどりますが、どうして「悪霊」をやるのかというところにつながるのかなと思います。
――事前のインタビューで、「悪霊」を選ばれた理由について「革命」という言葉を三浦さんは使われていましたが、それについてお聞かせ願えますでしょうか。
三浦 ちょっと話はずれますが、僕は森さんの映画は見て好きだったのですが、初めて肉声というか、今日お話を聞いて思ったのは、僕はサティアンにいかないですよ、直接。これは単なる性格の問題ですけど、でも森さんは行くわけで、現場に。僕が行けば違う映画ができるとおっしゃいましたけど、僕は行かないです。興味がない。解釈ということをおっしゃっていましたが、森さんの発言を新聞でも拝見していて感銘を受けるし、すごく大きいことを扱っているなと、今日もやはり敵が大きいのだなと思いました。個人がいて対象がいて世界がある。それはひとつのオピニオンリーダーだし、革命的な発言だと思ったんですね、拡大解釈をすると。今日の一番素晴らしい発言は、安部首相の文句言うのは、文句言ってもいいけど、それを選んでいるのは国民だし、国民のレベルの問題だということですね。私たちに全部返ってくるということですよね。そういうふうに世界と対峙して発言していったりすることと同時に、僕自身は解釈からできるだけはなれたところで、何とか個人に落としていけるんじゃないかと。つまり僕の演劇を見て三浦の解釈はこうだからといわれるとちょっと気恥ずかしいというか、同時に観客として森さんの映画をみたときに、森さんの解釈はどうなんだっていうことが通用するのかということで、いっしょになって今日共感したり、距離を置いたりするんですけど、僕はもうちょっと違う形で反解釈というか、解釈からずれていく。だから太田さんの仕事にちょっと似ているのかもしれない。原作があって、解釈の連続をしながら、誤訳しないように誤訳しないようにしているわけです。ただ誤訳はありますというのは究極の発言だと思いますけど。僕の芝居をみてどうしてあんな変なしゃべり方をするんですかといわれるんですが、客席にいて解釈から遠いところにいることができたら、それぞれが距離をもって観客が何かを鑑賞したり考えたりすることができれば、おそらく「革命」が起こるだろうと。僕は演劇人ですから、演劇にできることはやはりそういったことだと思っています。つまり、やばいわけですよ。劇場に直接お客さんが行って観るっていうのはある意味「集会」ですから、言論と集会の自由が演劇が唯一持ち得るもの、もちろん映画もそうなんだけど、演劇の場合はどうしても実演というか、その場にいないと表現されないものですから。そういう意味で「革命」という言葉を僕なりには扱っているんですけど。こんな大きい話は似合わないので言わないです。
――演劇はお客様と向き合って作品を発表し続けるので、お二方とはまた違ったお仕事だなと、お話聞いていて思いました。
三浦 まあ・・・まあね・・・。僕はずっと劇場にいるんですよね。森さんが自分の映画を観にいって客から感想聞いたっていうのは相当インパクトのある体験だと思うんだけど、僕はずっといるから、常に。だからそういう意味では効率悪いというかね。僕は演出家としては珍しいと思うんですが、常に劇場にいてその都度ダメを出したりして、変えていくんです。それはなんでかって言ったらお客さんが満足していないのが分かるからなんです。やっぱり、何か違うのかなとか、自分も客の一人でいる。そういった意味では違うかもしれないですよね。
森 三浦さんのおっしゃっていたことを受けてちょっと話します。僕の場合ドキュメンタリーでなおかついわゆるノンフィクションって言われる。自然な流れでそうなっちゃったんですが、つまり事実を取り扱うってところから始まっています。三浦さんは全く逆なわけですよ。舞台で、要するにそれこそ人が馬の被り物かぶって、それを馬だとして見るっていう世界ですよね。だから出発は全く真逆ですよね。でも進む方向は多分交差するところはあると思うんですよ。先ほど解釈のことをおっしゃっていましたが、僕はもう自分の解釈ということに疲れちゃったんですよね。今日も書籍を2冊持ってきましたが、もうね、むき出しなんです。自分でそれが嫌で・・・もう辞めます・・・もっと表現というのは豊かなものだと思うんですよね。僕の解釈なんてどうでもいいんですよ。その解釈をどのような形で豊かにしていくのかというのが表現だと思うんですよね。全然メタファーにできていないんですよ。本来ドキュメンタリーってメタファーのはずだったんだけど。
三浦 それはそうなんだけど、アクチュアリティーって問題が出てくるわけでしょ。つまり、ドキュメンタリーの場合は対象が確実に事件とか今起こっている問題っていう、選球眼が全部時事ネタなんですよね。悪い意味じゃなくて、時事性が強いと思うんですよ。僕がやっているのは演劇、フィクションなんだけど、結局はアクチュアリティーがなきゃだめなんですよね。いまどき別につまんないでしょ、バレエとかみたって。スポーツとしては面白いけど。まだ金メダル取ってくれたほうがおもしろいでしょ、時事性あるから。でもそうではなくて、どこにアクチュアルな点を持ってくるかって言うことをここ数年警戒していて、さきほどちらっと映ったイェリネクっていうドイツ語圏の作家が書いた作品は反原発の作品なんですよ。福島の「ふ」の字も出ないんですけれど、反原発なんて絶対言わないんだけど、超アクチュアルなわけです。書き言葉っていうのはものすごく織り込まれた難解なフィクションなわけですよ。そこで観客が反原発の演劇なんだって思うのか、思わないのかっていうのは情報操作が必要で、僕がすごいうらやましいのはドキュメンタリーはそれがいらない。事件がありました、いきました、カメラ参入しました、どういう風に見ますかっていうね。それはうらやましい、でも行き着くところは同じだと思う。そう意味では逆照射で迫っているんだけど。観客の中にアクチュアルな問題とフィクションの問題がどう絡んで行くのかということが表現になって行くんだと思います。先ほど太田さんのエピソードでなるほどと思ったのは、日本の映画を英語に訳すことが絶対に不可能だっていったのは、アクチュアルじゃないからですよ。彼女にとってリアリティがないからですよね。彼女と観客のリアリティがないし、もちろん母国語じゃないっていうこともあるんだけれども、それだけじゃない。そこが、これから問われていくことだと思うんですよ。

