SPECIAL ISSUE
特集

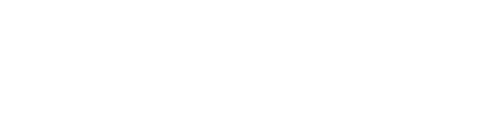
新作『駈込ミ訴ヘ』の足がかりをつくるべく行われていた、KAATでの最初の滞在稽古が終盤を迎えたクリスマス当日、地点の俳優3人による鼎談を行った。演出家・三浦基の思考、方法論を体現しながら、新たな表現を果敢に切り拓く彼らは、地点の創作の実質的な担い手であると同時に、俳優の表現領域をも更新する稀有な存在と言える。演出家とは違った視点から創作過程を見つめる、3人の証言から見た地点の稽古場とは。
構成・文:大堀久美子
――稽古の公開やポストトークなども積極的に行っている地点ですが、今日はさらに踏み込んだ創作過程について、最前線に立つ俳優の皆様から伺いたいと思います。現在、新作『駈込ミ訴ヘ』はまだ稽古の最初期の段階かと思いますが、どのような状況なのでしょう。
小林 どの作品の場合も、出だしが決まるまでの稽古は非常に難航します。三浦は作品を冒頭から順番につくらないと納得のいかないタイプで、出だしの5分のために一ヶ月くらい時間をかけることもある。作品のスタイルさえ決まれば、全体が転がり出すんですが。
安部 演技や俳優の表現に求めるところは、最近変化が出てきていますね。2003年からのチェーホフ・シリーズなどをやっているときは、作品スタイルを強化させていくというか、私たちの演技に対してもそのための強度を求めるところがあったけれど、太田省吾さんのテキストを題材にした『あたしちゃん、行く先を言って』(09〜10年)くらいからは開いていく演技、客席に分散させていったり、俳優同士の関係性も意識した表現になって来ている。それ以前は、誰が何を言おうと相手の方向すら見ず、各人の妄想のなかでしゃべっているような状態が常態としてありましたが、11月の『光のない。』では決定的な変化があって、「しゃべる互いを名づけていく」という行為にまで至った。
――内面へ向かう表現から関係性へと開いていく、というのは劇的な変化ですね。
石田 変化ということでいえば、KAATとの共同制作が始まったことが大きな要因になっていると思うんです。近年の地点は作品をかける劇場の規模が大きくなっていて、三浦も実際の舞台と同じスペースがないと、作品の絵を想像しづらい。だからKAATの、十分なスペースを確保した環境で創作できることがプラスになっているのは確かだと思います。
表現の芯が「関係性」に変わってきていることも、使う空間の大きさが関係しているのかもしれない。初期にやっていた「個々の妄想で」というやり方が、大空間では通用しない場合もあるだろうし。地点の作品は空間に、毎回かなり左右されていると思います。
小林 最近の傾向に、ガッツリした舞台装置を造らないということもあるよね。『コリオレイナス』(12年)もそうでしたが、舞台機構がそのまま装置になっているようなものが多い。作品にとって具体的なセットや装置のウェイトが高くないんだと思うんです。
それとリンクしているのか、演出の傾向としてはゲーム性が高くなっていることも変化のひとつじゃないかな、と。『光のない。』でお互いを「わたし」「あなた」と名づけ合うというシーンもある種のゲームから始まっているし、『コリオレイナス』ではフォーメーションを組む、中心人物の周りをグルグル回るというような動きが取り入れられている。初期作品では、目の前のテレビモニターを見つめながら妄想を独白する、みたいなシーンが多かったけれど、最近は皆で動き回って芝居を進めていくことが多くなったと思います。
――『トカトントンと』も『光のない。』でも、舞台装置に関して前者は逆開帳(※注)、後者は壁・床面にスリットを多用した開帳場(※注)など特殊な形状でありながら、デザインはシンプルなもの。そのなかで舞台上だけでなく、客席まで含めた劇空間と作品を繋げ、制御するために俳優の身体や声が非常に大きな役割をしているように見えました。劇空間に関して言えば、俳優は時に舞台美術の一部でもあり、またその声音は言葉を伝えるのみならず、音楽やサウンド・エフェクト以上の効果としても機能している、と。
安部 言葉、発語、動きなど表現する方法に関して、初期よりも要素や術が増えているのかもしれません。舞台上で、なぜ言葉をしゃべるのかを私たちはずっと考えてきた。「何をしゃべるか」ということより、「なぜ、どのようにしゃべるか」ということを主として考える状況を何年も続け、さらには動くことと発語することとの距離をコントロールするような術を見つけようとしてきた。これに関しては成功例がいくつかありますが、結局、作品ごとに新しい術を見つけなければいけないわけで。最近ようやく、この方向に進んでも良いんだ、という手応えを感じ始めたところなんだと思います。
――衣裳なども、俳優に負荷のかかるものが選ばれていますね。非常にヒールの高い靴やウェットスーツなど。
安部 あれは、KYOTO EXPERIMENT2012で上演した『はだかの王様』の衣裳用に自分で買ったものなんですけど。
小林 衣裳といえば、さっきの舞台装置とは対照的に割と具体的なイメージを表す場合が多いですね。『光のない。』のウェットスーツは津波や救助隊のイメージにリンクしていくし、『トカトントンと』は軍服や白衣のようなフォルムに、昭和なイメージの図柄や文字がプリントされていた。

『トカトントンと』(左:石田 大 右:小林洋平) 写真:青木 司
――作品の内容や背景、創作過程で見出したものを十全に観客に伝えるため、あらゆる手段、あらゆる媒介を駆使する、その貪欲な姿勢が地点の創作の現在なのかもしれませんね。受け止める観客側も、目だけ耳だけに頼らぬ観劇姿勢が求められる。
もうひとつ、題材である太宰治という作家に、三浦さんがこれまでの作家・作品と違った愛着を持っている、ということはご本人も公言していらっしゃいましたが、取り組みが他の作品と違うようなことはあるのでしょうか?
安部 明らかに違うと思います。こんなに題材となる小説や戯曲を、読み込んでいることも珍しいんじゃないでしょうか。『光のない。』の時とか、そんなに読んでないですよ。
小林 あいつ読んでない(笑)、ここだけの話ね。
石田 普段は、俳優に訊いてきたりするんですよ、「これどういう意味? 何言ってるの?」というように。
小林 そう、安部さんによく訊いてるよね。でも今回は、「全部俺に訊け、全てわかっているから」という感じ(笑)。稽古の最初に原作の「駈込み訴え」を、三浦が自分で全部読んだことがあったんです。「ここは作家気取りで書いてる、ここで太宰はお茶を飲んだね」とか逐一解説しながら。
石田 口述筆記で一気に書いたらしいですから、太宰の語り口にノって三浦が演じているような状態で面白かった。
小林 途中で本人が疲れちゃって。のどが弱いから枯れちゃって。
石田 なぜか日をまたいでやるという(笑)。「後半は明日」って。
安部 そこまで作家や原作を理解しているのに、「どうやって作品にするか」は、まだ三浦君にもわからない、というのも面白いですよね。
小林 三浦は、目の前にあるものからしか想像を膨らませられないんですよ。安部さんが履いていたヒールの高い靴も、見せられて初めて「いいね」と思う。今、稽古場で使っているオープンリールの録音・再生機の“ガチャッ”というスイッチの音も、聴いてみて初めて「この場面に何回か入れよう」と発想を進めることができる。即物的、反射的にその場で決める演出が多いので、さっき石田が言ったような実寸に近い稽古場や、道具類の揃いの良い環境が創作に不可欠なんだと思います。
石田 俳優の動きや発語も同じなんです。「誰かがしたこと」が、あとから皆が反復する基本の動作・動きになったり、即興でやってみた言い回しから、台詞の中のひとつの単語だけ違うイントネーションで言うという発語法になったり。もちろん、それらの表現の出発点、最初の姿勢や形は演出家の指示によるものですが、それを広げていくためには僕ら俳優が動かなければ始まらないことが多いですね。三浦は口癖のように「何か面白いことして」と僕らに言う。いつも一緒にやってるから、そうそう新しいことは生まれないですけどね(苦笑)。
小林 確かに即興で動いてみたり、しゃべってみたりはよくやります。
石田 それに「今のは100円」とか値がつけられたり(笑)。

『光のない。』(安部聡子) 写真:松本久木
安部 異なる手法を実践で使いながら、新たなテキストに対して使い方を変えてみることも出来るので、新作にはプラスになるような気がします。目標ははっきりあり、そこまではとりあえず色々とあがくことができますから。
たとえばチェーホフをやっている間は、翻訳者の言葉をある程度信頼したうえで壊していく作業をやっていましたが、太田省吾さんのときは言葉そのものの純度を追求し、太田さんのいくつかの作品から抽出した言葉を、レイヤーのように重ねながら立体化していきたいという欲望が湧いてきた。
太宰の『トカトントンと』は、舞台装置の段階で逆開帳と、舞台奥の壁に無数のパネルを配して“風を視覚化する”というアイデアが最初にあったので、そのなかで言葉が聞こえてくるようにと、テキストに対するアタックがそれぞれに違ったんです。
『駈込ミ訴ヘ』が難しいのは、『トカトントンと』と二本立てだから逆開帳という装置は一緒、けれど同じ姿勢では臨めないということでしょうか。立体化するための方法として、今のところは「駈け込む」という動きを頼りにはしているんですが。言葉自体は「語られた、しゃべられた言葉の記憶」とでもいうのか……言葉のなかにある「時間の厚み」のようなものが、カラッと出せたらいいな、と思ってはいます。
小林 同じ装置でも、『トカトントンと』と同じアイデアにハメては駄目。そこが危ういところですよね。そのために聖書の言葉や讃美歌、オープンリールに録音した音、聖書について対談した人の言葉まで、あらゆる異素材を取り入れては、取捨選択を繰り返しているわけだけれど。
安部 そのへんは私たち、『CHITENの近現代語』(11年)で鍛えられているかも。
石田 あれは転換期になる要素が多かったよね。ひとつのテキストを、どうやったら5人全員できれいにユニゾンできるか徹底的に追求したり。それぞれのリズムがあるから当然ズレるんだけど、「5人で一個になったらメチャメチャかっこいいよ」と求められ、必死にやるうちに、「2人だけ同時に発語する」とか「1人遅れる」とか色々なパターンをつくり、一つのテキストを変奏する方法を見つけた。あれをやってから変わったことが明らかにある。舞台上に出て行ったとき、自分は「誰」なのかを考えるにあたって。
安部 キャラクターが語るのではなく、「その場から聴こえてくるもの」をアンサンブルすることによって、空間を見聞きしてもらえる時間を観客に提示する、というようなことを試み続けているのかな。
石田 観客と、独特の関係性を求めているのかもしれない。
安部 その場にいる人に向かって、敵対や友愛のような、名づけられる関係性ではなく、でも何かをしゃべる。しゃべり続けることで、何かが起こる。
石田 しゃべるとか、語ることについて、地点ではあらゆる試行錯誤をしてきた。『トカトントンと』も『駈込ミ訴ヘ』も独り語りだけど、独白はとても難しくて、そうなるとさっきの“5人でひとつ”みたいなやり方に、糸口があるのかもとも思うんですよ。
『駈込ミ訴ヘ』は最初に「旦那さま」と駈け込んで来て話し出すけれど、話の途中で旦那さまはいなくなってしまう。稽古場で「語り手は、旦那さまは一体誰なのか?」と、出て来る人物について色々話しているけれど、当然のように誰もに太宰自身が重ねられている、自分で自分のことを話しているとも言える。ユダという太宰がキリストという太宰のことを、愛して憎んで……一人の人間のなかの葛藤、パラドックスをどう見せ、聞かせるか。『トカトントンと』は同じ語りでも、明確に居る一人の男がいくつかのエピソードを語り、つないでいく構成だけど、『駈込ミ訴ヘ』は語っていることの虚実、その語り手自体の存在もどこかあやふやで、そのぶん語られていることがねっとりまとわりついてくる感じがするんです。
――その違いを際立たせる手法を、今まさに模索しているんですね。例えば『トカトントンと』における玉音放送や、タイトル通りの“トカトントン”を打ち鳴らす大小のトンカチなど、作品を成立させるための手法、ツールを発見した瞬間というのは皆さん一斉に気づくものなんですか?
石田 気づくというより、「見つけた!」と思った瞬間に全員がそこに乗っかっていく感じがあります。
三浦から「コレでいく」というはっきりした宣言があることも多いし、執拗に時間をかけ、何週間も同じことを繰り返した後にようやく発見する時もある。
小林 そのためには、即興を繰り返すしかないんですよね。アイデアは瞬間に生まれてくるもので、考えてプランを立ててやった演技のほうが使われないことが多いんです。
安部 そういう突破口になる表現は、意味や物語とは距離を取ったものが多いですよね。『光のない。』のときもそうだった。「わたしたち」という一つの言葉を頼りに身振りやベクトルの多様性を発見していくことができたので。
石田 物語のある戯曲からチェーホフ以後離れていて、これまで扱ってきたテキストに地点の今の作品性も影響されてると思うんですけど、逆にシェイクスピアをやる時なんかは、物語ではない作品をつくるときのアプローチで、物語性の強い戯曲もつくれたりするようにはなっていますね。
――それは劇団という集団が蓄積したものでしょうね。最近の作品には常にそれが反映されている気がします。『光のない。』でも、あれは戯曲の体裁ではないのに、とても物語的に見ることができました。だから別に、あの大量の言葉も恐れなくていい、という気がして。
安部 「わたしたち」というものの見方を切り口にやっていこうと、本当にそこだけを頼りにしてましたね。「言葉を恐れなくていいんだ」と言ってもらえたのはすごく嬉しいです。
石田 今回は何が突破口になるのか……まだ時間はかかりそうですね。でも作品としても対照的だし、ひとりの作家のまったく違う側面を提示できる非常に面白い二本立てになると思います。
(※注)舞台の奥に行くほど床面の上がる傾斜のついた舞台を開帳場(八百屋舞台)と言い、反対に奥に行くほど床面の下がっている舞台を専門用語で逆開帳と言います。

