SPECIAL ISSUE
特集
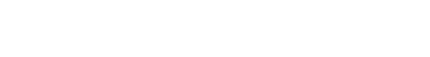

インタビュー・文 尾上そら
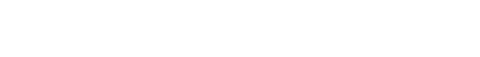
_
拝見した稽古内容について伺う前に、客席に向かって高くなっていく傾斜上の舞台面という特異な美術に目を奪われました。新作『トカトントンと』は太宰治の小説『トカトントン』と『斜陽』を主なテキストとした舞台と伺っていますが、この舞台空間はどのような意図から生まれたのでしょうか?
三浦 その質問に答える前に、作品の概要を少しだけお話ししたいと思います。この作品は今年3月、KAAT神奈川芸術劇場のこけら落とし企画〈NIPPON文学シリーズ〉のひとつとして上演された、芥川龍之介の小説や関連した書簡をもとにした『Kappa/或小説』に続く作品です。
日本の近現代文学を劇化するという企画に取り組み、取り上げるべき作家を考えたとき、僕には芥川に続く作家として太宰治以外思い浮かばなかった。これは、既に作品の特設Webサイトに掲載されたインタヴューでも話したことですが、太宰はそれくらい重要であり、以前から愛読していた作家でもあるからです。
太宰に限らず、日本の近現代文学では戦中から戦後にかけての時期、日本が一度焼け野原になり、そこから復興していく過程を描く作品が多い。ですから、それら小説を演劇化するためには舞台上に焼け野原の“何もなさ”、更地のような状態が必要だと考えたのです。
そもそも僕は、舞台空間を考えることから創作を始めるケースが多いうえ、メインとなる短編『トカトントン』が日本の敗戦とそれを肯定する主人公の想いに始まり、本来であれば希望の象徴になりそうな復興のための建築音にも似た“トカトントン”という音に、強烈な虚しさを感じるというストーリーで、舞台上の“何もなさ”は主人公の虚無感を表現するためにも必須だと思えた。
では“何もなさ”をどう表現するか。ベタに考えれば砂や土を敷き詰めた床面、ということになりますが、それに近いことは以前の作品で経験済みで。何かもっと抽象的な表現をと探すうちに「床面が見えなければいい」と思いついたのです。そんな発想を形にする以前にもうひとつ、今回は常とは違う要素が創作の初期に加わっていました。
KAATとの共同制作は、京都から地点の演出家と俳優、制作が横浜へ入り、日本有数の劇場スタッフがこれを迎えてくれる形で進んでいきます。この「出会い」を二度目の今回さらに有効なものとするため、美術プランを思い切って畑の違う方にお願いすることにしたのです。それが劇場の方が紹介して下さった建築家の山本理顕さんでした。ご著作を拝読して面白かったうえ、山本さんも僕の舞台作品を面白く観て下さった。今回題材となる太宰治という作家に関心を持っているということも、二人の接着剤になりました。そうして生まれたのが今回の美術プランなのです。

前回公演 『Kappa/或小説』 2011. photo: Takehiko Hashimoto
_
舞台奥の部分は、小さな正方形の薄いパネルが無数に吊るされた“揺れる壁”のようになっていますが。
三浦 これは「奥の壁が風によって揺れるのはどうか」という理顕さんにいただいたアイデアです。復興という刻々と変化する時代を象徴するものとして、変化を招き促す「風」も舞台で表現したいという話が理顕さんとのミーティングで出た。そのために振動や風で揺れ動き、表情を変えるパネルの壁をつくる。これは理顕さんの肝入り作品です。
傾斜の舞台についてもうひとつ加えるならば、俳優が斜面を上ってくることでその姿は次第に大きく見えもすれば、逆に下ることで小さく見えなくなりもする。劇中での人間の見え方、スケール・コントロールが効果的に行える装置だという確信も持っています。
また舞台下に扇風機を仕込み、実際の「風」に俳優が影響を受ける様も見せられたら面白いなとも考えています。
さらに舞台上で「風」を表現することは、僕にとって太宰治の作家としての視線を表すことにもなる。
太宰治は「無頼派」の名の通り、非常に破天荒な人生を歩み、それを作品に転化した作家として世間一般に知られています。でも今回、僕はその前提を全部取り払いたい。少し俯瞰すれば太宰が破滅的な私小説作家というだけでなく、日本という国で「表現」をする、その方法を熟考していたことが分かる。実際、戦中の検閲にあっても『お伽草紙』『右大臣実朝』など優れた作品を書き、後には、今回テキストとして使う『斜陽』など大ベストセラーも生み出していますから。
また『トカトントン』では、虚無的で自己の存在認識が薄い主人公をつくり、玉音放送に始まる天皇制の問題、時代の転換など、当時の人々が受けた「時代の風」を巧みに描写してみせた。作家・太宰が戦中戦後を貫いて持ち続けた日本という国、日本人に対する批評的視線を、目に見えない舞台上の「風」に繋げて表現できれば、今まで誰もやったことのない<舞台における「風」の提示>にもなるのではないか、と期待しているところも自分の中にあるのです。
極めて抽象的ですが、新たな挑戦として「虚無感」を視覚的に表現するための「見えない地面」と、時代の変遷を物語りつつ、時に作家の視線を表す「風」をモチーフにした、この美術プランで今現在創作を進めています。



_
『Kappa/或小説』もそうでしたが、今回も対象となる作家の一般的なイメージとは異なる実像に迫り、同時に作家の生きた時代の空気を観客に体感させる作品になりそうですね。
三浦 そう、太宰治という作家の人生論ではなく、太宰治という人間がどう当時の日本で生きていたのか。空襲のさなか、防空壕で怖がる子供にだましだましお伽噺をしたり、焼け野原が復興していく様をどんな立ち位置でどう眺めていたのか。太宰が感じた戦後日本の「時代の空気」、それを僕は今回「風」と言っているのですが、そういうものを表現できたときに多分、僕にとっての「太宰治」を舞台でやれたことになるんじゃないか、と。
また、それら「時代の空気」=「風」を扱うことが、近現代の日本文学、固い言い方をすれば日本人論に取り組むことにもなる。演劇を通じて当時の日本人論に目を向けてもらえたら、その先の時代にも繋がるような考え方が出てくるんじゃないかと思う。「太宰を演劇でやる」と言うより、「太宰の(時代に対する)選球眼」を通して、現在の私たちの状況を見つめてみたい、と今回は強く思っています。
_
創作方法についても伺いたいと思います。テキストの抜粋部分、発語のタイミングや分担などは俳優の方々と取り決めてあるものの、立ち位置や動きなどに関しては発語と並行して様々な展開が試みられ、全てが同時進行でつくられていくように見えました。演出家と指揮者の仕事・役割を類似したものとして例えることもありますが、三浦さんは指揮しつつ全体の空間構成にも目を配り、さらには奏でる楽曲の創造も同時に行なっているようでした。これは地点のスタンダードな創作方法なのでしょうか?
三浦 まあ、そう言えると思います。ただ、このシリーズは「小説を演劇にする」という点が通常とは違う。戯曲と違ってカギカッコの発語すべき台詞だけが続くわけではないので、地の文章にあたる部分をどう発語するかなど、普段とは違うハードルがあるわけです。
本来、太宰治を知りたかったら文庫を手に入れ、家で寝る前にじっくり読めば良いんです。でも劇化する以上、その舞台を観た観客が太宰の小説を読んだときに匹敵するか、或いは凌駕するような体験をしてもらわなければいけない。でなければ戯曲でないものを演劇化する意味はないんです。
そのためには「こういうルールで演劇は行われます」という前提を僕らがまず越えなけれいけない。これは非常に複雑な作業です。
今日ご覧頂いた場面も多分、本番には半分くらいしか踏襲されないでしょう。そんなトライ&エラーを繰り返しながら、どんな表現が小説本体を読む体験を凌駕するかを、ふるいにかけているのが今です。そのふるうザルの目が、細かい時と大きい時の差が僕は非常に大きいらしい、最近こそ自覚的になりましたけれど。「今日はザルの目を大きくして、このくらいふるいましょう」と言ったかと思えば、急に細かいところにこだわったりしてしまう。台詞の細部、一言一言の抑揚までをチェックする稽古の直後に、非常に粗い目のザルで作品の全体を見直す作業が僕の中には近しく同居できてしまう。そこは確かに特徴的かもしれません。それに、だいたいが固定メンバーでやっていますから、ザルの目の大きさや種類は全員が共有していますし、粗い目のザルを使いながら小さいことを考えるような、真逆の作業を同時にやることにも慣れている。そこが特徴的に見えるんでしょう。
今の段階では皆さん、「これはどこへ飛んでいくんだ?」と思ってらっしゃる方が多いでしょうけれど(笑)、稽古がもう少し進行していくと「この場面を引っ張ろう、ここをもっと引き上げよう」というそれぞれのシーンに対する思考が結合していく瞬間が出て来る。それが現場レベルでは、一番スリリングな時期でしょうね。
地点の三浦演出は台詞への細かい指示、「『父と母と』の「ち」と「は」を同じレベルで強調して」みたいなことばかり言っているように思われるかも知れませんが、それだけでなく、取り上げた台詞をバッサリとカットするような可能性も稽古場では常にある。非常に体力を使う、徒労の多い作り方だという自覚はあるんですけれどね。


_
テキストはありますが、口立て(台本を渡さず、劇作・演出家が俳優に口頭で台詞を伝え、その場で覚えさせながら進める方法)で行う稽古に近いようにも思えます。
三浦 なんと言うか……普通、普通とは何かという議論も別にありますが、普通はテキストをもらって演出家はそれに従って劇を構成していく。先程指揮者がたとえに出ましたが、指揮者の場合は楽曲が先にあり、演奏時間もやるべきことも決まっている。
でも僕が今やっていることは、題材として作家・太宰治の存在はあるけれど、それを文字通り読むのではなく、「そこに在る太宰をどう見るか?」という作業。だから、どうしてもテキストの切り貼りや引き出しの入れ替えなどはせざるを得ない。ただ、その作業は作家のそれとは全然違うと思っているんです。
ご覧いただいた場面の中にずっと笑い続ける人物がいましたよね? しつこくしつこく。彼の役割を成立させるには、彼の笑いを別の人物に“もらい笑い”させればいいんです。それを「感染」と僕は言っていますが、もらい笑いが生じることで舞台上の時間が少し進む。「こういうことか!」と一瞬納得することを発見できる。
何故こんなことをやるかというと、普通はテキストが1から10まであるとすると、私たちはそれを読んだり聞いたりすることで、自分の中で「物語」を完結させられる。でも今のような作り方を進めていくと、「物語」とは別の部分で、太宰治という人が何を考えていたのかが突発的に表出する瞬間があるんです。戦後日本で「戦争に負けてよかった」と言うときのニヒルな笑いとか、そういうものが。
このことを僕は、薬を投入することで太宰の傷口をガバっと広げるような行為だと考えています。傷口を広げると、周囲への感染がさらに広がるというようなことに僕は興味がある。僕の演出は、処方箋とでもいうのか、題材に何か投薬している感覚に近いんです。僕の投薬により太宰の憂いや希望、さらに言えば「文体」、太宰文学というものが一体何なのかを観客は目の当たりにすることができる。これがめざすところ。演出家としての感覚は日本文学に限らず、チェーホフをやるときも同じです。
_
演出家というより医師ですね。
三浦 そう。だからこの考え方だと、始終相手の何処に傷があるかを探ることになる。地点の稽古で試行錯誤が多いのは、僕が傷を探すため、しっちゃかめっちゃかをやるからでしょうね。だから、なかなか台詞が決まらず俳優たちも難渋する(笑)。また、普通の戯曲ならば俳優は与えられた台詞だけ覚えて自分の役を成立させることもできますが、僕らがやっている作業は、全員が全部の台詞を読まなければいけないし、極端な話、全部覚えないとできないとも言える。俳優の負担は相当大きいと思います。継続した作業は必須ですが、徒労になることも多いので。言い方を変えれば三浦演出はイイ加減で、俳優がどこまでやってくれるかにかかっている、とも言えるでしょうね(笑)。
_
地点の俳優陣が持つ発語や身体の卓越したコントロール力は周知のことですが、それは三浦さんが求める表現に必要不可欠なものとして、獲得されたものなんですね。それにしても、演出家を医師になぞらえるのは興味深いたとえです。
三浦 たとえ話が多くなりがちなんですね、僕は。ただ、医者は本来患者を選べないので「じゃあ三浦、シェイクスピアにも投薬出来るのか」と言われると、それは正直どうなのか。一回もやったことがありませんしね。まあ、医者にも専門があるので眼科医に皮膚の病気を看せても、結果はかばかしくないような気がします(笑)。一番良いと思う状況は、医者の立場である僕にも太宰という病気が伝染ったときじゃないかな。病気を診て、投薬しているつもりが感染してしまっている。医者が患者に恋してしまうような状況の創作こそ、本当は全ての観客が観たいと思う舞台のようにも思えますが。

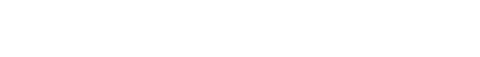
_
拝見したシーンの中には太宰の小説だけでなく、玉音放送の断片や賛美歌などもありました。それらをなぜ加えられたのでしょう?
三浦 『トカトントン』は日本の敗戦、つまりは玉音放送から始まる小説ですから、どんな演出家にも効果音的に玉音放送を使うという発想はあると思います。先に言った「時代の風」のように、当時の出来事を象徴するものとして玉音放送は非常に大きなものでしょう。 また、小説のラストには聖書の引用もある。芥川も太宰も、自分の枕元に聖書を置いているような人たちで、聖書の言葉や思想を自作のなかでも重用していました。なので、玉音放送にしても賛美歌にしても全然関係ないテキストや素材というわけではなく、小説と作家の周辺にあるテキストをいかに再構成し、上演できるかという実験をしているんです。
また、それとは別の興味も実はあります。小説を俳優が喋るということは、先程も言ったように非常な苦労を伴う行為ではありますが、僕はこれを新しい取り組みとして考えている。小説と一口にいっても具体的には「私は~と思う」という感情を説明する描写か風景描写、主だった文章はだいたいこの二つに分類できるんです。
それ以外にどんな種類の文章があるかと言うと、たとえば玉音放送がそれに当たる。今回は口語訳を使います。先の賛美歌や聖書の言葉、またこれはまだ使うかどうかわかりませんが、『トカトントン』の後半には当時行われた「新円への切り替え」にちなみ、郵便局にせっせと貯金する女のエピソードが出てくるのですが、それに関連して「何円、何円」などと貨幣のレートを読み上げていく声も素材になる可能性はあると思います。
_
作品の中で語られる言葉のバリエーションを増やすわけですね。
三浦 小説とは違う文体、違う表現、違う聞こえ方の言葉を掛け合わせることで、以前から興味があったこと、人間が日常的に喋る言葉と俳優が喋る戯曲の台詞、その距離や差異を検証できるのではないかと考えているんです。
私たちは日常的に思っていることをただアウトプットする、たとえば「私は○○です、私は嬉しい」というような、経験値から生まれた言葉だけを喋っているわけではありませんよね。もっと違う、多彩かつ大量の情報が次々にインプットされていて、そこから得たものも自ずと喋る言葉に加わっていると思うんです。
人間を器に、この場合は俳優ですが、俳優を器として考えたとき、どういう情報を投入すれば面白く喋り出すかということを、今回検証できると思っているんです。多様な言葉を人間のなかにいかに詰め込むか。それは僕が演出家として、俳優との作業で一番重要視していることです。
僕にとって「ここで泣け」と言って泣けない俳優はダメですが、近代以降ずっと「ここで泣け、ここで笑え」というような“なりきり演技”、そんな演技の完成度を上げるため、俳優たちは一貫して努力してきた歴史がある。でもその歴史は既に終わっていて、俳優の演技や演劇にはもっと別の可能性があると考えているんです。
_
その可能性とはどういうものですか?
三浦 “なりきり”はできて当たり前。俳優はもっと不条理な、もっと「意味で回収されない言葉」を喋れるはずで、それは今回の太宰は別にしても、常に僕の興味のあるところなんです。
僕の作品を観た方が戸惑うのは、その辺りに原因があるように思います。「何故あの俳優はあんなことを喋るのか?」と。それは、発語される言葉から意味が回収されないからなんです。
舞台上の類型的ななりきり演技とそれを見るという行為は近代的なもの。劇中でダメージを受けた人間を見て「この人は哀しさのあまり自殺するだろう」と感じる、そういう見方です。そんなはずはないですよね?
私たちはそんなものより、もっと恐ろしい現象を日々目にしている。哀しくて人間が死ねる時代はまだ良かった。今はそんなことで人は死ねない、もっと世界は複雑で不条理です。その原因を掘り下げていくと、そこには「言葉には出来ない情報」があり、今の僕の一番の興味はそんな「言葉にはできない情報」を舞台上でそれでも言葉を使った上で表現することにあるんです。

_
「意味が回収されない、意味に縛られない言葉」をどう扱うか、それらの言葉と俳優の身体の関係性をどう結ぶかは、日本の現代演劇のなかで重要なトピックになっていることだと思います。もうひとつ、発語した言葉に対して別の俳優が「ウソです!」と次々に打ち消していく場面も興味深かったのですが、それも三浦さんの検証のひとつなのでしょうか?
三浦 『トカトントン』の主人公、虚無的で自己の存在認識が非常に薄い、物語の語り手であるこの男は、小説の終わりで「ウソばっかり書いたような気がします」と言います。そこからあの、他者に対して「ウソです」と言い募るシーンはできました。
僕にはこの男が、たとえば台風のときに暴風域へとわざわざ赴き、仕事とはいえ強烈な風雨にさらされるニュースキャスターのような、いわば視聴者に現状を伝えるための「生贄」的存在に思えてならない。そして、その役割は俳優の仕事にも近いと思うのです。
キャスター個々には名前がありますが、風雨にさらされる「生贄」には名前は必要ない。
語り部の男も同様で、結果、創作中のこの作品は、俳優が特定の「誰」なのか分からない状態で進行していきます。
恐らくこの作品は、一人の人間が紡ぐ物語というよりも「断片」の集合体というほうが、その性質をよく表せる種のものなると思います。そして作品が完成したときそこには、僕が以前から取り組んでいる、<物語に頼らず俳優が「誰」かを演じることができるのか?>という現代演劇に対する問題提起と、その先にあるであろう新たな表現に向けての可能性を探る糸口があるように思えるのです。
_
今作に託された演劇的な実験や検証に、さらに興味が湧きました。このNIPPON文学シリーズを手がけたことは、三浦さんが演劇でやりたいこと、やろうとしていたことを推進する原動力になったのでしょうか。
三浦 それは……直接的に結びつくことではないと思います。僕は作家ではないので、作家のように言いたいこと・好きなことを表現している訳ではないのです。このシリーズであれば、「日本文学を舞台化する」というお題というか発注を受け、その創作の過程で今僕が強く関心を寄せることと結びつけられるものが見えてきただけなので。
ただ題材に関して言えば僕は無類の太宰好きで、彼の筆力の高さ、語り文化の影響が色濃い文体、職人作家としての高度なスキル、東北人特有の含羞や卑屈さへの共感など元々持っていましたから、それは創作の原動力にはなっていると思います。
_
先に仰ったような「感染」の確率も高いのでは?
三浦 そうでしょうね。だから同時に危険性も感じてはいます、好き過ぎて創作上のハンドリングや作家との距離感を見誤ることがないように、と。
_
秋、稽古前に行なった今作のためのロングインタビューでは「エンターテインメントを創る」とも仰いましたが、その想いに変わりはありませんか?
三浦 いわゆる娯楽性の高い作品という意味ではなく、「観客に対して作品を通し語りかけ続ける努力を惜しまない<優しさ>を持って創作に臨む」という指針のもとに創るエンターテインメントは、今回に限らず、今後も創り続けようと考えているものです。太宰自身は大ベストセラー作家ですし、自身の「道化」への憧れを作中にも書いていますから、題材としても最適でしょう。
演劇という芸術は観客がいて初めて完結するもの。僕が言うエンターテインメントを成立させるためにも、当然観客の存在が不可欠です。客席を満たす観客すべてを置いてけぼりにしないため、創作の過程上にどれだけ対話を繰り返したか、本番ではどれだけ観客に語りかけられるか。登場人物や場面に託された喜怒哀楽を増長させるだけの安易な演出を徹底的に廃し、開幕から終演まで観客が作品とともに歩み、思考し続けられる作品を創りたいと思っています。
_
最後に、戦後の復興期を背景とする今作は、東日本大震災後の日本の現在に重なるものも多いように思います。二つの「復興」を重ねる、創作の意義をどのように考えていらっしゃいますか?
三浦 震災があったから戦後の焼け野原を舞台とする作品を選んだという訳ではありませんが、あれだけの大きな出来事ですから僕自身も当然影響は受けていると思います。シリーズの前作『Kappa/或小説』はKAATでの公演初日が震災当日で、そのため一回しかここでは上演できませんでしたから。
ただ、劇中には敗戦からの復興だけでなく、天皇制問題や経済についてなど、時代の大きな変わり目が描かれていて、それらはどれも現代に重なる側面を持っている。復興ということだけでなく、今、私たちが時代の転換点に居るということを共に考えられるようなものができれば、非常に意義のある作品になるのではないかと思っています。


