SPECIAL ISSUE
特集
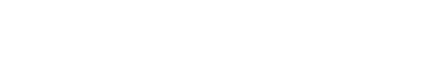
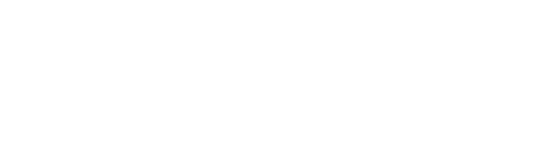
三輪眞弘〈オリンピックに向かう社会〉とイェリネク『スポーツ劇』のテキストから触発されたことを、各執筆者の研究分野と結びつけて自由に書いていただくリレー形式の特集記事です。『スポーツ劇』にはスポーツを巡る言説が散りばめられています。オリンピックの開催を2020年に控えている日本社会において、各エッセイを通じて読者や観客の皆さんが改めて思いを巡らせるきっかけになればと思っています。
よしおか・ひろし
京都大学大学院文学研究科教授。1956年京都生まれ。専門は美学芸術学、情報文化論。著書に『情報と生命』(新曜社)、『思想の現在形』(講談社)他。批評誌「Diatxt.」(京都芸術センター2000-2003)編集長、「京都ビエンナーレ2003」ディレクターなどを務める。京都国際舞台芸術祭実行委員会委員。
「勝つことではなく、参加することに意義がある」と、小学校の授業で教わった。まもなく1964年の東京オリンピックが開催される頃で、オリンピックの精神、スポーツマンシップとは何かというようなことが、道徳の時間の話題にされたのである。その後、聖火ランナーが学校のすぐ近くの国道を走るのというので、沿道でそれを応援するために、日の丸の小旗をみんなで作らされた。
勝つことより参加することが大事だなんて、いったいどういうことだろう? それは子供には分からなかった。プロ野球でも大相撲でも学校の運動会でも、勝つことがいちばん大事なのは当たり前に思えたからだ。オリンピックだって同じじゃないだろうか? 誰かがそのように訊くと、違うと先生は答えた。勝つことよりも大切なことはあるのだ、と。「近代オリンピックの父」と呼ばれた、クーベルタンというフランスの偉い人がそう言ったのだそうだ。
「参加することに意義がある」というのは、本当はクーベルタン男爵(Pierre de Frédy, baron de Coubertin, 1863-1937)が自分で考え出したのではない。男爵は、アメリカ人のタルボット大主教(Ethelbert Talbot, 1848–1928)がロンドンで行った説教の一部をパラフレーズしたのである。大主教がその説教を行ったのは、1908年夏のことだ。それはちょうど、ロンドン・オリンピックが開催されている時だった。試合ではイギリスの審判が下す判定に対しアメリカ人たちが不正だとイチャモンをつけたりして、ちょっとした騒ぎになっていた。この事態を憂慮した大主教は7月19日、セント・ポール教会でのミサにおいて、オリンピック選手や関係者も多く含まれる聴衆に向かって、次のように語りかけた。
「…確かに誰かが言ったように、スタジアムにおけるこの国際化の時代には、危険な要素が含まれています。もちろん選手たちはみんな、スポーツのためだけではなく、自分の国のためにも競い合っている。こうして新たな競争が作り出されます。とはいえ、たとえイギリスがボートで負けたり、アメリカが徒競走で他を引き離したり、あるいはアメリカがかつての強さを失ったとしても、それがいったい何だと言うのでしょう? あらゆる偽りを越えて唯一確実なことは、真のオリンピアの教えの中にあります。それは、試合そのものは競争や褒賞よりも優っているということです。聖パウロが教えたように、[地上の]褒賞はどうでもいいものだが、われらの褒賞("Our prize”)はけっして不正に買収されることはない。勝利の桂冠を頂くのはただひとりかもしれないが、競い合うことの喜びは万人に共有されているのです。」
「参加することに意義がある」という表現とは、だいぶ印象が違う。ここでは「真のオリンピア」や「聖パウロ」が呼び出されているからである。上の文を理解するには、スポーツの価値は個人や国家を越えた存在によって支えられていることを認める必要がある。つまり試合が競争に優るのは、それが神によって観られている出来事だからなのである。大文字の「われら(Our)」の褒賞というのは、勝者に与えられる地上のメダルではなく、試合に参加しそれを共に体験するわれわれすべてに神が与える褒賞という意味だと思われる。
もしも「参加することに意義がある」という言葉がこうした考えを起源とするならば、その意味は「負けてもいい、頑張ったこと自体が美しいんだよ」というようなことではない(そんなんだったらただの負け惜しみ、せいぜい慰めにすぎない)だろう。そうではなく、頑張って競い合う姿が常に人間を超越した存在によって観られていると考えることで、はじめて筋が通る言葉なのである。と同時に、ここでもうひとつ注意すべきなのは、上のタルボットのお説教がそうであるように、そこでは超越者、神サマはそれほどハッキリとは名指されてはいない、ということだ。
古代オリンピックが近代オリンピックになって何が変わったか? グローバル化したというのはもちろんだが、本質的な変化は、ギリシアの神々がキリスト教の神にとって代わられたということである。古代ギリシアの、あまりお行儀のよくない(のもいる)神サマたちに代わって、厳正だが近寄りがたいキリスト教の神サマが、オリンピアを統括することになった。けれども時はすでに20世紀で、多くの人はもはやあからさまに「神サマ」とは言いにくくなっていた。その結果、オリンピックにおけるスポーツはひたすら人間的な価値、「たとえ勝てなくても頑張ることは素晴らしい」みたいな、人間的あまりに人間的な価値へと矮小化されていった。そして、そこからワケが分からなくなってゆく。
20世紀も後半になると、ギリシアの神々もキリスト教の神もますます影が薄くなってゆき、それらに代わって別な神サマがオリンピアを支配するようになった。それは「お金」である。といっても、モノとしてのお金が神サマに取って代われるわけはないのであって、不在になった神の座に居座ったのは、お金をめぐる人間の、集合的で匿名的な欲望である。といっても、競技者たちがお金のために試合をするようになったというような意味ではない。むしろその逆である。選手たちは、高度に技術化された訓練を受け、たゆまぬ努力をし、記録や限界にひたすら挑戦する、そういうピュアな存在であらねばならない。そのようにお金は命じるのである。
人々がもっと多くのお金を出すように、選手たちはその「ひたむきさ」によって人々を「感動」させるように、強制されている。いわばこうした「ひたむきさ」や「感動」が、オリンピックという欲望機械を動かす燃料として搾取されるわけである。この意味で、選手たちもまた犠牲者である。「純粋な」スポーツが「汚い」産業や資本主義に操られているのではない。むしろ、スポーツの「純粋さ」「ひたむきさ」「感動」といった言葉それ自体が、子供たちに「夢」を与えたり日本を「元気」にするといった言い方と同様、誰かが莫大な金儲けをするためのシステムの一部だからである。だからそれらの言葉は骨抜きにされ、意味を失い、空々しく響く。
意味を失った言葉に私たちは取り囲まれている。そのことをまともに批判しても、言葉を金儲けや権力闘争の手段としか考えない人々とは、議論にならない。「子供たちに夢を与えて何が悪いんですか?」などと開き直られるのがオチである。けれど大事なことは、言葉それ自体に咎があるわけではないということである。事態は絶望的だけれど、私たちは正しく絶望しなければならない。結局のところ、私たち自身が言葉を丁寧に扱い、それによってより多くの人が言葉を大切に使い続けるように、地道に仕向けてゆくしかないのではないか? ぼくはそう考えている。自分がすることで世の中が変わるかどうか分からなくても、人は正しいことをし続けるべきだからだ。これはつまり、「参加することに意義がある」と同じではないだろうか? この点で、絶望はそのまま希望へと変貌する。地上の勝利は得られなくても、われらの褒賞は不正に奪われることはないからである。
そんな悠長なこと言ってて本当に大丈夫なのか?と心配する人もいるだろう。 たしかに今の世の中、自分の身の回り——たとえば大学の人文系学部の縮小や廃止という政策は、ようするに言葉を大切に扱うという人間の営みそれ自体への攻撃にほかならない。国や文科省が、国民に(彼らがだましやすいように)「もっとバカになれ」と命じているのだ——を見ていると、こりゃあほんとにオシマイじゃないか?と思えるのは確かだ。「言葉を大切に扱う」なんて呑気ことで、本当に大丈夫なんだろうか?そう考えてジタバタすることもある。…でも結局のところ、たとえ大丈夫じゃないとしても、ぼくは最後までそうし続けるしかないし、し続けるのだと思う。

