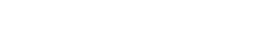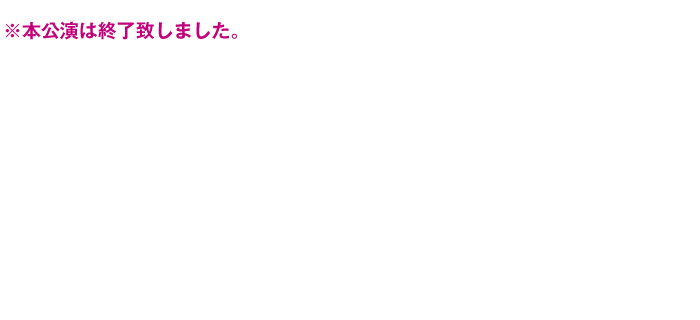Story
作品概要
古代ギリシアの復讐の物語に登場するヒロインたちをモチーフに、メディアによって翻弄される現代人の姿、
戦争の代替としてのスポーツ、身体から逃れられない人間の宿命について、イェリネクは自らを媒体として語り続ける。
パパ ママ イエス 違う
沈黙から沈黙までの長広舌。
圧倒的な集中とイメージの乱高下。
『光のない。』に続く、地点によるイェリネク作品第2弾!
膨大なモノローグの応酬によって構成されるこの戯曲では、戦争の代替としてのスポーツについて繰り返し語られ、スポーツ観戦に耽る大衆と戦争を黙認する国民が重ねて描かれます。
全編に渡って溢れるスポーツのイメージ。随所に散りばめられる、ギリシア悲劇の引用、実在のスポーツ選手やスター俳優、そして著者自身のエピソード。
理性的にスポーツ批判が展開される一方で、雑多なイメージのひしめく異常なエネルギーと集中力。
イェリネクが差し出す、新たな「語り」の可能性に応えるべく、地点は「決して黙らない演劇」をつくります。
作者について

エルフリーデ・イェリネク(1946-)|Elfriede Jelinek
詩人、小説家、劇作家。オーストリア生まれ。ビューヒナー賞をはじめ受賞多数。小説『ピアニスト』(1983年)は2001年にミヒャエル・ハネケによって映画化され、同年カンヌ映画祭でグランプリを受賞した。2004年、「豊かな音楽性を持つ多声的な表現で描いた小説や戯曲によって、社会の陳腐さや抑圧が生む不条理を暴いた」功績によりノーベル文学賞を受賞。『スポーツ劇』は1998年にウィーンのブルク劇場で初演された。見どころ
死者の前で沈黙する前に――マスに対抗するモノローグ
イェリネクの分身と考えられる「エルフィ・エレクトラ」の“やっと静かになりました。”という台詞で始まり、やはりイェリネク自身と考えられる「著者」による独白“しかし、それはすでに終わりの後、そして、静寂静寂、物音もせず。”で締めくくられるこの戯曲は、モノローグの応酬で構成されており、沈黙から沈黙までの間に繰り広げられる長広舌であるともいえます。演劇において前提とされる登場人物相互の関係性や心理は一度棚上げにされ、対話(ダイアローグ)はほとんど形をなしていません。イェリネク戯曲が難解と言われる所以です。しかしながら、父の死に際して、黙することを放棄し、語り尽すことによって対応しようとするこのテキストは、堪え難い現実、あらゆる理不尽、不正への徹底抗戦の意志を強く感じさせるものでもあります。イェリネクが敵視するのはテレビの前で沈黙する群衆。饒舌によって神経を逆撫でするこの戦いの受け皿として彼女が劇場を選んだのは、新たな「語り」の可能性をそこに見出すからなのでしょう。長きに渡って「語り」を追究してきた地点が、イェリネクの文体を借りて、決して黙らない演劇を出現させます。ギリシア悲劇の主人公から実在のスポーツ選手まで
『スポーツ劇』には、ホーフマンスタールの『エレクトラ』とクライストの『ペンテジレーア』が引用されています。母親によって殺されたアガメムノン王の復讐を誓い、弟のオレステスが母殺しを実行する『エレクトラ』。女権国家の戦士が恋人アキレスを虐殺し、自らも命を絶つ『ペンテジレーア』。いずれも女性を主人公とした復讐のドラマであり、痛ましい結末が待つ悲劇です。また、オーストリア出身で“アーニー”の愛称で親しまれるシュワルツェネッガーと、彼に憧れ、筋肉増強剤の過剰摂取で死亡したボディビルダーのアンドレアス・ムンツァーをはじめとする実在のスポーツ選手のエピソードが随所に散りばめられています。いにしえから続く愛憎のドラマと、メディアによって翻弄される現代人の悲劇が交錯し、作品世界を織り成します。コロスとコロッセウム
ギリシア悲劇はじめ、オリンピックの起源としての古代ギリシアをモチーフにしているこの作品では、コロスが主要な登場人物として描かれています。『スポーツ劇』の初演は伝説的な成功をおさめていますが、アイナー・シュレーフによる当時の演出では50名のコロスが舞台全面に整然と並び、30分近くに渡って体操をしながらテキストを唱和したといいます。『光のない。』では足だけを見せた合唱隊(コロス)が印象的でしたが、三浦&三輪によって『スポーツ劇』ではどのようなコロスが出現するのか。見どころの一つとなることは間違いありません。また、木津潤平による舞台美術が、2016年1月にリニューアルオープンするロームシアター京都の空間をどのように変容させるのか。どうぞご期待ください!『光のない。』劇評抜粋



photo: Takuya Matsumi
(ポストドラマ演劇の)難解さが気鋭の演出家から想定外の創意を引きだすのだから、演劇は面白い。地点の三浦基が演出し、三輪眞弘が音楽監督をつとめた東京芸術劇場プレイハウスの舞台は日本語の母音を共鳴させるヴォイス・パフォーマンスを突きつめ、異様で、ひりつくような感覚を観客に刷りこむ意外な試みだった。テキストを再構成し、その力を意味ではなく音に還元していく上演は「わたし」と「あなた」の境界を溶解させ、観客に当事者性の認識を迫る。安部聡子の次第に熱を帯びる音楽的発声が素晴らしい。遺体ともみえる役者のシルエットや足首だけを見せる一種のインスタレーションがかもしだす不気味さ、四角形の光の窓から放射状に広がる世界の終末的な風景、それらが消えがたい印象を残したことは確かだ。
内田洋一(「シアターアーツ」2012冬号,2011年)
乱反射するイメージが流動化する「わたしたち」/「あなたたち」のあいだに入り込み、さらに三輪の音楽がその流動状態を加速させる。三輪自身が各所で述べているように、音楽(芸術)とは決して生者のためだけのものでなく、死者や未だ見ぬものたちへと捧げられる。すなわち、イェリネク―三浦―三輪による『光のない。』は、鞣(なめ)された「わたしたち」/「あなたたち」という存在の肌理(きめ)を逆撫でして、対立項が都合良く造り出されていることや、「わたしたち」/「あなたたち」という尺度の変換を照らし出す。それは、ひょっとしたら震災以前/以後というレトリックに重ね合わせるようにして乱立する区分自体への批判となるような峻厳なメタ的作品であり、震災前/後という割り振りで物事を押し進めようとする議論への反省的思考ですらあるかもしれない。『光のない。』は、震災や原発問題を性急に追い越し、完了した出来事へと捧げられるレクイエムとしてあるのでは決してない。それは単にポスト3・11という過去形にした状態で、安易な人道主義の装いをまとって示されるものではないのだ。追い越し、進むのではなく、その場にあえて滞留し、声をもたない存在を自らのうちに呼び込んで、語らせること。(中略)イェリネク―三浦―三輪の三者が変奏し合う『光のない。』は、“わたしたち”の存在や存在様態そのものに関与しているのである。
太田純貴(「アルテス」,Vol.4 2013年3月)